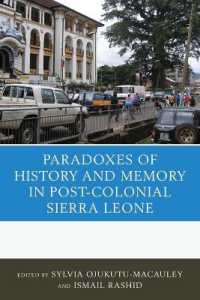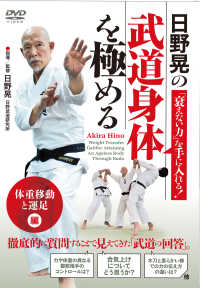内容説明
二一世紀、グローバル化する世界。“帝国”は脱領土化し、「言説空間」に闘争の場を移す。ネグリ/ハート『帝国』の問題提起を受け、「言説的権力としての帝国」によるヘゲモニー闘争として世界を読む画期的論考。
目次
第1章 “帝国”状況を/から透かしみる―取り締まられるアメリカ都市空間、「ホームランド・セキュリティ」、人種
第2章 「規制帝国」としてのEU―ポスト国民帝国時代の帝国
第3章 “帝国”はどこにあるのか?―モンゴル国の土地私有化政策に見る“帝国”の現れ
第4章 カール・シュミットの「アメリカ帝国」論
第5章 ソ連崩壊後のスラブ・ユーラシア世界とロシア帝国論の隆盛
第6章 国際関係研究における「帝国」と“帝国”
第7章 帝国化する世界システム―「長い二〇世紀」とその帰結
著者等紹介
山下範久[ヤマシタノリヒサ]
1971年生まれ。東京大学教養学部卒業。同大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。1995‐97年、米国ニューヨーク州立大学ビンガムトン校(ビンガムトン大学)社会学部大学院にてイマニュエル・ウォーラーステインに師事。北海道大学大学院文学研究科助教授。専門は、世界システム論、歴史社会学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ステビア
21
定義がちゃんとしてないからみんな好き勝手なこと言ってる印象2024/08/06
無重力蜜柑
13
かつて国際関係論において帝国の研究が大流行したことがあった。その起爆剤としては一方にネグリ・ハートの〈帝国〉があり、他方にブッシュ政権を始めとするアメリカ「帝国」の横暴があった。だがこの二つの帝国の意味合いが全く異なるように、その流行はアカデミックというよりはイデオロギー的、消費的なものだった。帝国はゼロ年代のバズワードだったわけだ。そんな帝国概念について、二〇〇六年時点での中間決算を行なおうとしたのがこの本。七本の論文が収録されており、いずれも一種の「帝国論」論、メタ国際関係論のような内容になっている。2024/10/18
Toska
5
7人の研究者による帝国論集。現代の「帝国」は具体的な領土などを持たず、言説空間の中にのみ存在する…分かりにくい。正直、何故そのテーマが「帝国」につながるのか理解できない論文もある。そんな中、「規制帝国としてのEU](鈴木一人)は非常に面白かった。実はコスト高だったかつての植民地帝国のあり方から脱却し、軍事に頼らず規制だけを押し付けていくスマートなやり方で、しかし確実に自己の利益を追求していくEU。成程これは確かに帝国だと思わざるを得ない。2021/09/27
Daring
0
帝国論とは何だろうか。帝国概念のイデオロギー的還元からの脱却という点については多面的な帝国概念を提示することで目的を達成していると思われる。しかし特定の政治的・社会的実態への投影を回避するという目的は本書によって十分に達成されたとは思えない。つまり帝国概念の再定義についての議論にいまいち納得出来なかった。「長い16世紀」についての議論や19世紀以降の帝国不在が例外的であるとするならばp.228-229この議論は非常につかみ所のないものに感じる。2011/12/01