内容説明
二〇世紀、論理学と哲学を横断して起きた「知の革命」。パラドクス・無限・不完全性と完全性・言語と論理・計算機科学と論理学などをキーワードに、論理をめぐる哲学探究の刺激に満ちた現在を、気鋭の著者陣が解説する。
目次
第1章 論理学と哲学
第2章 嘘つきのパラドクス
第3章 ソリテス・パラドクス
第4章 完全性と不完全性
第5章 論理と数学における構成主義―ある議論
第6章 論理主義の現在
第7章 計算と理論
第8章 自然言語と論理
著者等紹介
飯田隆[イイダタカシ]
1948年生まれ。東京大学教養学部卒業。同大学大学院人文科学研究科修了。慶應義塾大学文学部教授。専門は、言語哲学・数学の哲学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
SOHSA
14
哲学からの派生的興味から初めてきちんとした論理学の本を読んだが、初心者にはかなりハードルが高い。以前から論理の構成や展開には数学との共通性が多いのではという印象を抱いていたが、本書を通じてそうした景色が少しずつ見えてきたような気がする。おそらく内容の半分すら理解できていないと思うが、本書は私に論理学の持つ未知の魅力を示してくれた。2013/04/22
★
1
論理の哲学に関する入門書。イントロダクションも兼ねている1章で論理の哲学の発展史が描かれ、2章以降では嘘つきのパラドックス、ソリテス・パラドックス、完全性定理・不完全性定理、直観主義と構成主義、新論理主義、カリー・ハワード同型対応、自然言語の意味論などといった、論理の哲学における重要なトピックが紹介されている。いずれの章も平易な言葉で書かれているうえ、論理学についての知識がそれ程なくても読めるように工夫されており、細かい配慮が行き届いていた。2012/11/14
☆☆☆☆☆☆☆
0
(当時の)若手研究者による論理哲学の概説書。ちょっと難しいところもあるけれど、論理式が理解できなくても学説史的な概要はわかるようになっているので、最初の一冊としては手ごろ。元技術屋としてはプログラム理論に一番関心を惹かれる。人間の認識とプログラミングの対応関係。2014/12/10
222242@es
0
次に何を読むかの参考のために非常に適しているだろう。だが、自分の興味とは微妙にずれており、いくばくかかゆい所に手が届かない感じを受けた。 2013/05/06
321
0
表記の仕方が分かりにくいけれど、内容が凄く良い。2010/10/02
-
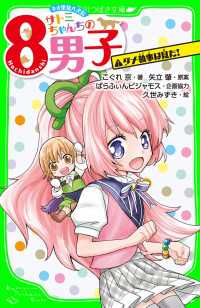
- 電子書籍
- ネオ里見八犬伝 サトミちゃんちの8男子…






