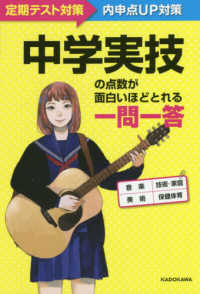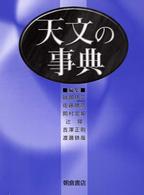内容説明
馬賊が誕生した清末期。あるものは官憲の銃弾に倒れ、あるものは混乱を潜りぬけ略奪者から脱却し、軍閥の長として中原の覇権をうかがう。覇権に最も近づいた男=「東北王」張作霖とその舞台の激動の歴史をたどり、併せて日本にとって「満洲」とは何だったのかを考える。
目次
第1章 「馬賊」はなぜ現れたのか?(「馬賊」のイメージ;軍隊へのまなざし ほか)
第2章 張作霖登場―「馬賊」から「軍閥」へ(張作霖はなぜ「馬賊」になったのか?;帰順とその後の活躍 ほか)
第3章 王永江と内政改革―軍閥期の「満洲」(張作霖と王永江の出会い;王永江の奉天省財政改革;保境安民―王永江の内治政策;郭松齢事件から王永江辞任まで;張作爆殺)
第4章 日本人と「馬賊」(第一次満蒙独立運動(一九一一~一二年)
第二次満蒙独立運動(一九一五~一七年)
日本人の「馬賊」体験
「馬賊」・匪賊たちの群像
匪賊を支えるもの―編成、出身、心性)
終章 現代日本にとっての「満洲」・「馬賊」(「馬賊」とは何だったのか;新しい「満洲」像へ)
著者等紹介
渋谷由里[シブタニユリ]
1968年、東京都生まれ。日本女子大学文学部卒業後、京都大学大学院博士課程修了。現在、富山大学人文学部助教授。専攻は中国近代史
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
崩紫サロメ
22
「馬賊あがり」「日本の傀儡」として過小評価される張作霖の再評価を通して、馬賊とは、満洲とは何かを考察する。まず、著者は馬賊を「匪賊」とは異なり、「保険隊」という社会的ステータスを得ており、張作霖の場合は王永江という優秀な行政官僚のもと、警察行政が刷新され、税務機構が整理され、鉄道建設・大学設立を果たした。つまり「馬賊」から満洲全域を統治する「地方政権」へと変容している。そして、中国全土に号令する政治的指導者へと変貌するため、張作霖は中途半端な状態である「馬賊」を卒業した、とする。2022/10/31
Takeshi Kubo
4
「馬賊」と張作霖について、そのイメージを掴むことが出来る本だと思います。 しかし、満洲という地域を背景に生まれた「匪賊」でも軍隊でもない「馬賊」は、張作霖という人物を輩出しながらも、その当人によって抑圧され消えて行ったというのは、中々皮肉だと感じます。結局は、変転する満洲という場の情勢に呑み込まれることを避けられない存在だったように、思いました。2014/11/30
kimoiue
3
蒼穹の昴シリーズからこちらへ。張作霖の生き方を知れて良かった。 たとえ爆殺されなくても王永江が亡くなったあとは厳しかったんだろうなぁ。 人物の写真も多く、大変勉強になる本でした。2020/06/25
birdrock
3
浅田次郎の「中原の虹」で張作霖があまりにもかっこよかったので、史実を知りたくなり読みました。読めない漢字の人名とやたら長い組織名がいっぱい出てきたので読み進むのに難渋しました。「中原〜」にも登場する王永江が張作霖の満州統治のキーパーソンだったことがよく分かります。また当時の河南以南の中国人(=漢人)が満州のことを必ずしも中国の一部と考えていなかったかも知れないことを思うと、もしあの時代に日本がこの地域に手を出さなければ、今の中華人民共和国という国の形や日中関係は大きく違ったものになっていたと思います。2014/12/12
ぐま〜
3
このあたりの中国史は結構複雑で分かりづらいのですが、視点を「満州」において史実を扱っているので読みやすかったです。2012/11/20