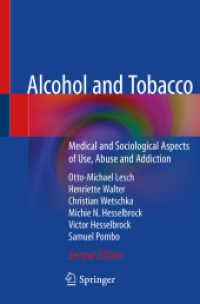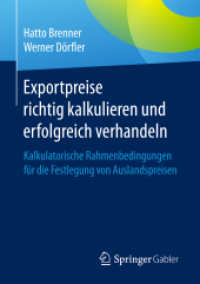内容説明
世界の近代化はいかに成しとげられたのか。なぜ日本だけが、非西洋世界でいち早く近代化をとげたのか。ブローデル・ポランニーの理論を包摂し、ウォーラーステインを超えて展開する、画期的世界システム論。
目次
第1章 世界システム論を超えて
第2章 グローバルな「長期の一六世紀」
第3章 近世帝国と日本
第4章 近世帝国の解体とグローバリゼーションの歴史的起源
第5章 「近代化」概念の脱構築と「日本」
終章 グローバリティの変容と日本
著者等紹介
山下範久[ヤマシタノリヒサ]
1971年生まれ。東京大学教養学部卒業。同大学総合文化研究科博士課程単位取得退学。1995‐97年、米国ニューヨーク州立大学ビンガムトン校(ビンガムトン大学)社会学部大学院に留学、世界システム論の理論的指導者イマニュエル・ウォーラーステインに師事。現在、北海道大学大学院文学研究科助教授(歴史文化論講座)。専門は、世界システム論、歴史社会学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。