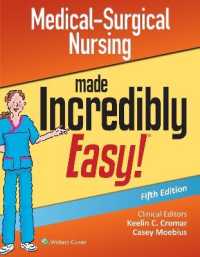内容説明
紀元前に千キロ単位を航海し、太平洋の島々に移住した人々とは。そして、彼らと我々の驚くべき関係とは。遺伝子、言語、遺跡、そして神話に残された痕跡を縦横に読み解き、広大な大洋を渡った「海人」の実相に肉薄する。
目次
序章 ボエッジ・オブ・リディスカバリー
第1章 海人の民族学―アジアの海浜にて
第2章 海人の黎明―スンダランドからオセアニアへ
第3章 海人の始動―オーストロネシア系海人の登場
第4章 海人の展開―未知の海域へ
第5章 海人の精華―ポリネシア人のからだとこころ
第6章 海人の戦略―移住の戦略と航海術
第7章 海人の小宇宙―シンボルとしてのカヌー
第8章 海人日本へ、そしてアメリカへ
終章―海人論から学ぶもの
補章 比較言語学と歴史言語学
著者等紹介
後藤明[ゴトウアキラ]
1954年生まれ。東京大学大学院修了(専攻・考古学)、ハワイ大学大学院で人類学と言語学を専攻。人類学博士(ph.D.)。現在、同志社女子大学現代社会学部教授。日本、台湾、東南アジア、オセアニア、北米で調査に従事
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しんさん
6
面白かった! 東アジアからメラニシア、ミクロネシア、ポリネシアへの紀元前の移住は、なぜ、どのようにして行われたのか。日本を含む海人、移動する人々の精神文化。地図も電話もない時代に、未知の海を1000キロ単位でカヌーでいってしまうなんてすごすぎる、、、。2024/05/06
koz kata
4
我々にとって1番身近なポリネシアンはハワイ出身の力士たち。彼らの体格が素晴らしいのはそういう体格の人々でなければ南洋の海上で凍死しかけるような過酷な新しい島を見つける為の航海に耐えられなかったから。風に逆らって島の探索をしたのは見つからなかった時に風の力を借りて帰って来やすいから。 年功序列や二重統治システムはポリネシアにもあったので日本では「これは日本にしかない」と思われているものも目に入っていないだけでかなりありふれているらしい。ほっとするね!2016/06/18
つみれ
2
マオリがニュージーランドに住み始めたのは鎌倉時代くらいって聞いたときに、へえ!ってなって全くこの本忘れてるわとなったので再読。今回はグーグルマップで位置を逐一確認してかなり島や諸島の位置と名前を覚えたけど、マルケサス諸島とか探すのほんと大変なんよ、ようこんな島へたどり着いたなとなる。一方でかく見えるハワイやニュージーランドは緯度移動で大変とようやく覚えた。▼移動の圧に戦争はどれくらい関わったんだろう、メラネシアの内陸には入り込まなかったのは平和に棲み分けたからだけとは思えないし、マオリは好戦的だというし。2023/07/08
つみれ
1
行ったり来たりしてたんだよね〜って言われるとそりゃそうだって思うけど、やっぱり何時代について言われても驚く。鰐は鮫になるって因幡の白兎じゃんってなったので著者の他の著書も読みたい。2022/11/02
浪人
0
日本人との関係は謎のまま残った。2012/09/06