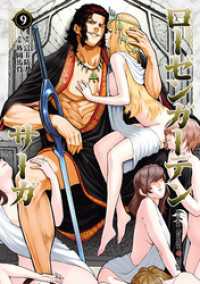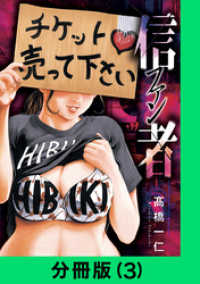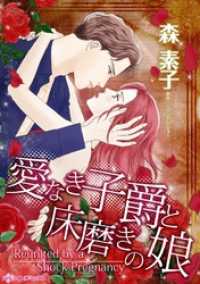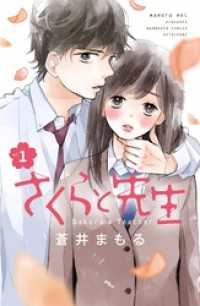内容説明
明朝第三代、永楽帝。甥、建文帝を倒した簒奪者。その負い目は彼を史上屈指の「天子」たるべく駆り立てる。鄭和に命じた南海大遠征、五度にわたるモンゴル親征、北京遷都…。華夷秩序を建てなおし、中華の「世界システム」を構想した男の見果てぬ夢を描きだす。
目次
第1章 中華という名の世界
第2章 大明帝国の誕生
第3章 皇統のゆくえ
第4章 奪権への階梯
第5章 歴史の翻転
第6章 失われた時のなかで
第7章 天命の所在
第8章 クビライを越えて
第9章 華夷秩序を統べる者
第10章 永楽帝の遺産
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
崩紫サロメ
15
永楽帝の評伝の形を取りながら、明初とは何だったのかを問い直す。元・明に一定の連続性を見出す宮崎市定の立場を継承しながら、更に永楽帝がクビライの継承者として、クビライを更に超えた「世界システム」を構築していく過程を描く。西洋的な「近代」とは違う中国的「近代」の起点として明初を捉え、著者の得意とする華夷秩序と天命思想から朱元璋や永楽帝の政策を読み解く。永楽帝に関して、傍観者として中立的視点を持つ朝鮮王朝実録を用いているのも興味深い。2020/06/08
鯖
13
中華思想の説明から入り、永楽帝を通して初期明王朝を描く。甥からの王位簒奪から粛正の嵐、己の評価を正当たらしめるための外交政策で鄭和の大航海へという流れ。中華「世界システム」の構築においてフビライもなしえなかった日本の属国化を勘合貿易をもって血を流さず成し遂げたという指摘にはなるほどなーと。winwinだったんだなあ。元王朝の最期は天変地異が続き、黄河が大洪水、疫病(同時期にヨーロッパでも猛威をふるったペスト説もあり)とみると卵が先か鶏が先かという部分はあるだろうけど、易姓革命もまんざらじゃないんだなあと。2018/12/09
ピオリーヌ
11
『陸海の交錯』を読み、同著者のこちらにたどり着く。東アジアの国際関係を律するシステムの完成者、永楽帝を通してみる明初体制が画かれる。今まで概略しか知らなかった靖難の変についての知識が得られた。また唐の太宗、何よりフビライを意識した永楽帝の生きざまが強い印象を与える。資料として、より中立的な資料とされる朝鮮王朝実録を引いている点が興味深い。2020/07/29
Fumitaka
3
明の永楽帝を、彼が伝統的な中華思想というか華夷秩序の実現という考えの中で行動していたと分析。親父の朱元璋の分封体制も前任者モンゴル帝国の制度を模している(p. 72)というのが面白い。実際には「反モンゴル」どころかクビライを模した部分さえあり、足利義満に割と甘い対応をしたのもクビライも下せなかった日本を臣従させたから(p. 203)だとする。まあ竜の指の数からしても日本が冊封体制の中にあるのは明白ですからね。そういやあの竜の形が日本に伝わったのはいつ頃からなんだろうか。『龍の起源』には書いてなかった。2022/08/04
富士さん
3
明太祖の伝記を再読したので、流れで再読。改めて太祖の毒々しい魅力を実感しました。この人もそうですが、秦始皇帝はじめ唐太宗、玄宗など中国史上の君主には高名であってもどこか翳があります。何をやっても貶されるのが指導者の常の中、複数指導制が不可能だった中国の指導者であることはどうあっても完全な名声とは程遠く、誠実であればあるほど無力感に苛まれる事であったでしょう。しかし、太祖からはこのような人の目を気にする可愛げを感じません。劣等感をも利用して陰謀を巡らせるふてぶてしさ。おそらくそれは、天命を受けた乞食の矜持。2014/08/10