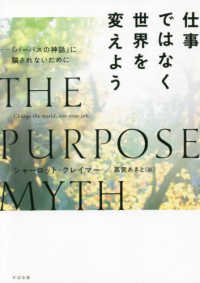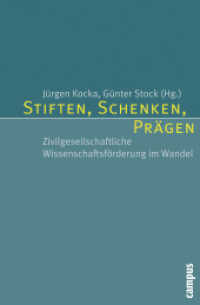内容説明
やまと絵、浮世絵、水墨画…。なぜ「絵」と「画」が使い分けられているのか。明治初期、西洋化の波のなかで「絵画」という語が成立したのはなぜか。日本美術の誕生・創出を「ことば」から探る先鋭的美術史。
目次
第1章 「近代日本美術」とはなにか―時間と空間の枠組
第2章 美術の文法
第3章 ジャンルの形成―「日本」への論争
第4章 美術の環境―階層・行政・団体・コレクション
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ik
3
日本美術史と西洋美術史の間に感じていた違いが非常にすっきりとわかるようになった 言葉や制度といった枠組みから規定される近代日本美術の性格、特徴がとてもわかりやすく参考になる一冊2011/03/07
のの
2
前半はことばの成立、後半は制度について。 画や図の使われ方とかは興味深かった。 やはり眼の神殿の影響は大きかったんだなぁ。2011/03/03
たぬき
1
世界史が西洋史な ごたるあるよ2014/05/28
なおた
0
「以後、明治29年東京美術学校(※今の藝大)に「西洋画科」が新設され、翌30年には日本画の美術団体「日本画会」が結成される…中略…こうして「西洋画」は、「日本画」の相対概念として成立し、制度に支えられながら展開してゆくことになる。(本書86ページ、第3章「ジャンルの形成」より引用)本書の終章「日本美術史の創出」も大変参考になった。「日本美術」とは「言説によって記された言語の体系」である...というのが著者の論旨であった。確かにそうかもしれないな...と、ふと思った。2025/07/27