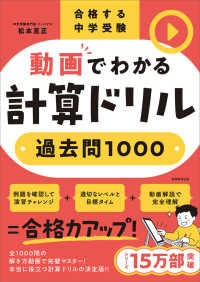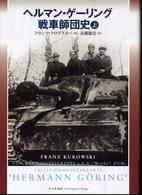- ホーム
- > 和書
- > 新書・選書
- > 教養
- > 講談社ブルーバックス
内容説明
分子・細胞レベルを操る自己組織化テクノロジーとは。ランダムから秩序を作りだす現象が自己組織化である。脳の神経細胞から血管細胞、味細胞、嗅細胞、さらに心筋細胞に見られる自己組織化の現象を応用して人工知能や味覚センサー、においセンサー、マイクロロボットの実用化を目指す自己組織化テクノロジーの最前線を紹介する。
目次
第1章 自己組織化とはなんだろうか
第2章 自己組織化のしくみ
第3章 粘菌は自己組織化する
第4章 脳がつくるリズムとパターン
第5章 生命と人工生命の進化
第6章 生体パーツの自己組織化を操る
第7章 味覚を再現する
第8章 嗅覚を再現する
第9章 生体パーツを取り込むデバイス技術
著者等紹介
都甲潔[トコウキヨシ]
九州大学大学院博士課程修了。九州大学工学部助手、助教授を経て、九州大学大学院システム情報科学研究院教授
江崎秀[エザキシュウ]
1958年、福岡県生まれ。九州大学工学部電子工学科卒業。同大学院修士課程修了後、東芝医用機器技術研究所勤務を経て、近畿大学産業理工学部電気通信工学科教授。専門はバイオエレクトロニクス
林健司[ハヤシケンシ]
1960年、福岡県生まれ。九州大学工学部電子工学科卒業。同大学院博士後期課程修了後、九州大学工学部助手、鹿児島大学工学部助教授を経て、九州大学大学院システム情報科学研究院准教授。専門は電子機能デバイス工学
上田哲男[ウエダテツオ]
1947年、大阪府生まれ。大阪大学理学部化学科卒、北海道大学薬学研究科修了。薬学博士。日本学術振興会、フルボルト財団、ブリティッシュ・カウンシルの研究員、北大薬学部助手、同助教授、名古屋大学教授を経て、1998年より北大電子科学研究所教授
西澤松彦[ニシザワマツヒコ]
1965年、宮城県生まれ。東北大学工学部応用化学科卒業。同大学院博士後期課程修了後、大阪大学大学院工学研究科助手、東北大学大学院工学研究科助教授を経て、東北大学大学院工学研究科教授。専門は電気化学、バイオチップ工学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
うーさん
中島直人
yori
calaf
-
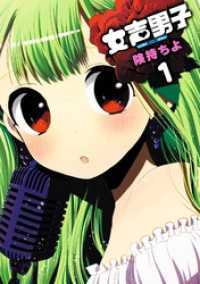
- 電子書籍
- 女声男子1巻 ガンガンコミックスONL…
-
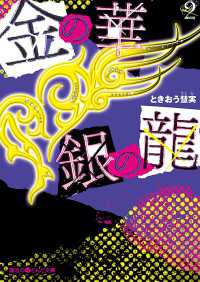
- 電子書籍
- 金の華 銀の龍(2) 魔法のiらんど文庫