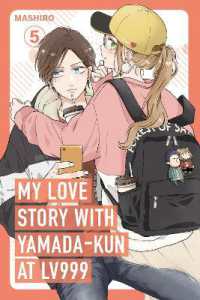内容説明
スヌーピーはクッキー中毒がなおらない。サリーは勉強ぎらいがひどくなる。ペパーミントパティはピンボケ病がすすむ。チャーリー・ブラウンは「心の相談室」通いがやめられない。思いどおりにならないこと、めんどうくさいことに囲まれていても、みんな、あっけらかんと生きていかれるのは…!?その心理を臨床心理士の岩宮恵子が掘りさげる。
目次
1 気がすまない人
2 なるふりかまわない人
3 度が過ぎる人
4 困惑させる人
著者等紹介
シュルツ,チャールズ・M.[シュルツ,チャールズM.]
1922年、アメリカ・ミネソタ州に生まれる。漫画家。1950年10月2日に「ピーナッツ」のタイトルで新聞連載が始まり、以来、50年にわたりスヌーピーたちの活躍は続いた
谷川俊太郎[タニカワシュンタロウ]
1931年、東京都に生まれる。詩人。1967年頃から「ピーナッツ」の翻訳を手がける
岩宮恵子[イワミヤケイコ]
1960年、鳥取県に生まれる。臨床心理士。鳥取大学医学部精神科での臨床を経て、臨床心理相談室を個人開業。2001年より島根大学教育学部助教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
与太郎
4
シリーズ2作目。最高だ。最高すぎる。色褪せない輝きと面白さ。スヌーピーたちの物語を一生懸命になって読んでいた子供のころと、意識がリンクするような感覚。どれもこれもが宝石のように愛おしい。今になって読むからわかる面白さもある。けれど、あのころ読んだからわかる面白さも確かにあって、つまり全年齢でも楽しめるところがスヌーピーという漫画の魅力なんだと思う。2011/01/05
ykshzk(虎猫図案房)
2
今年の目標は少し自己中心的になること。半分は英語の勉強に、半分は自分の心のためにと思い読んだ。「いい子をやめるにはどうしたらよいか」が載っているものではないので、登場人物達の自由で個性的なふるまいに触発されるしか無い。マーシーに近いであろう自分としては、はめをはずす、気の済むまでやる、なりふり構わない、のはなかなか大変なことだ。ルーシーのようにはなれないが、自分の欲求に素直になる意味で、ご飯にかける情熱をストレートに表現出来るスヌーピーのような部分を持ちたい。何歳になっても読めるのがスヌーピーの面白さだ。2016/01/13
Yuko Osuka
2
★4 犬が眠ってるところを見てたら宿題ができませんでした、ってのが好き。2013/01/20