内容説明
塀の内側に堕ちた武井保雄・武富士前会長が、自らの金銭観、人生論を赤裸々に語る―巨大化したサラ金業者を牛耳るドンたちの素顔に迫り、コマーシャリズムに隠された、業界の懲りない非人道的実態を告発。一連の山口組ドキュメントなど、現代社会が内包するきわどい問題に、果敢に斬り込み続ける著者だけが書ける、「拝金主義のカリスマ」たちの本性。
目次
序章 武富士「サラ金帝国」崩壊す
第1章 「武富士」武井保雄の知られざる真実
第2章 「プロミス」神内良一の“転向”
第3章 「アコム」木下恭輔は“金貸しのエリート”
第4章 「アイフル」福田吉孝の意気軒昴
第5章 「レイク」浜田武雄が剥がされた良識派の仮面
第6章 サラ金を操る銀行の戦略
第7章 その手口と被害者たち
第8章 サラ金の“明日なき戦い”
第9章 “ポストサラ金”「ヤミ金」と山口組の関係
著者等紹介
溝口敦[ミゾグチアツシ]
ノンフィクション作家、ジャーナリスト。1942年、東京都に生まれる。早稲田大学政治経済学部を卒業。出版社勤務などを経て、フリーに。2003年、『食肉の帝王』(講談社)で第25回講談社ノンフィクション賞受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
23
一時期、街角にはサラ金の無人契約機が並び、テレビでは連日コマーシャルが流れていた。過剰に貸し付けてその利息で十分成り立つサラ金業界と、 大手金融機関との関係についても言及されていいる。最近は、その大手大銀行がサラ金と結託してクリーンなイメージのサラ金になっている。しかしその実態は、結局多重債務者を増やすことになっていると感じた。2014/03/24
Daisuke Oyamada
8
本書は1983年に刊行された内容に改訂及び追加し、2004年に刊行されたちょっと古めの本です。現在は大分改善されているのかも知れませんが、まさに「サラ金地獄」とはこうやって堕ちて行くのかと、恐怖を感じるような内容でありました。 レビューにこんなことを書いている人がいました。 この本は337ページに及ぶ大作だが、わずか一言で要約できます。「金貸しは儲かる」それだけです。 まさにその通り・・・ https://190dai.com/2023/05/30/武富士-サラ金の帝王-溝口敦/2023/05/29
luther0801
6
半沢直樹曰く、「結局、銀行は金貸しなんです。だからこそ、人を見る目が必要なんです」。ただ、今の金融機関には、いわゆるサラ金との違いをあまり感じない。カネを動かして、自らの利益につなげてるだけ。拝金主義、決して否定はしないが、まぁ、限度が有る。2013/10/14
さとうよ
5
滅び行く彼らの最盛期を描いたルポです。滅び行く物語はいつも美しいものですが、そんな情緒を持たせないですね。サラ金を被害者ではなく、業者から描く事で被害の実態(素晴らしいビジネスモデル)を上手くあぶり出している。被害者側から描くとどうしても「借りたものを返すのは常識」といったモラル論が出てくるが、それは元本を大きく上回る金を返さねばならないサラ金の構造を理解していないから出てくる言葉だ。溝口氏は言及していませんが、こんな阿漕なやつらにCMを打たせたテレビ、新聞さんは自らの社会の公器としての責任をどう考えてい2011/07/28
牧神の午後
5
武富士に限らず業界主要企業の執筆時点(80~90年代)でのプロフィール、拡大戦略の紹介。拡大戦略といっても、どうやって金を貸して回収してということになるわけで、当時社会問題となったサラ金地獄のメカニズムが貸す側の立場から解説されている。当時わが世の春を謳歌していたこれらの企業が、グレーゾーン金利の問題で今や銀行の傘下に収まっていることに時代の流れを感じる一方で、当時のサラ金の資金調達手段(銀行からの迂回融資等)の解説を読むと、銀行がなりふり構わなくなってきたとも見れて興味深い。2011/03/08
-

- 電子書籍
- 闇金ウシジマくん【タテカラー】 トレン…
-
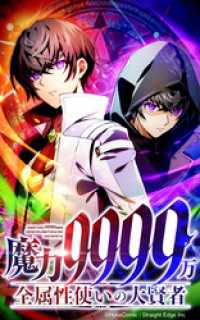
- 電子書籍
- 魔力9999万 全属性使いの大賢者【タ…
-
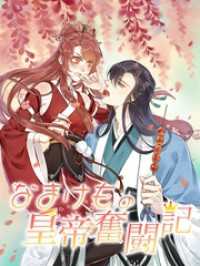
- 電子書籍
- なまけもの皇帝奮闘記 第23話 道観の…
-

- 電子書籍
- Mr.Clice 8 ジャンプコミック…





