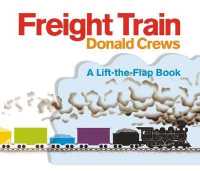内容説明
「善良」な人たちが撒き散らす注意・挨拶・お願いなどのテープ放送や、機械音への抗議。戦う哲学者は管理標語や看板、大垂れ幕にまで戦場を拡大した!都市や農村や行楽地などの「文化空間」に決定的なずれを覚える哲学者の「からだ」と、平均的日本人の「からだ」の違いとは?日本人の感性の根底を見据えながらも、そのずれから生じる怒り・憎しみ・不安・人間不信・人間嫌悪、そして「差別」に感じる恥ずかしさを告白する「かつてない日本人論」。
目次
第1章 音漬け社会との果てしなき戦い―その成果(大反響;ジャーナリストたち ほか)
第2章 拡大する戦場(音は人を狂気に近づける;音は皮膚のウチに侵入する ほか)
第3章 定型的な言葉の氾濫(標語ノイローゼ;「エレベーターの扉をこじ開けないでください!」 ほか)
第4章 日本人のからだ(からだとしての文化空間;文化空間における図と地 ほか)
第5章 共生は可能か(解決は難しい;思想はいつも現実の前に屈伏する ほか)
著者等紹介
中島義道[ナカジマヨシミチ]
1946年、福岡県に生まれる。東京大学人文科学研究科修士課程を修了後、ウィーン大学哲学科を修了。哲学博士。電気通信大学人間コミュニケーション学科教授。専攻は時間論、自我論、コミュニケーション論など
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
テツ
19
街を歩いていると勝手に耳に入ってくる音の数々。BGMも呼び込みも注意喚起の放送も確かにうるさい。そうしたことについて克明かつ執拗に抗議する中島先生の姿は素晴らしい(ただの偏屈おじさんと紙一重な部分もあるけれど) 自分が不快に感じるコト&モノに対して感度を下げることなく、徹底的に不快さを抱きしめ掘り下げ分析し、どうして不快なのかと考え続けられることは感性のマジョリティにのみ与えられた特権なのかもしれませんね。2019/08/28
Shunsuke
2
私も都心に引っ越してきたとき町の喧騒に嫌気がさし、著者と同じく耳栓とヘッドホンをしていたことがある。今では気にならなくなってしまったが(著者からは激しく嫌われる人種であろう)。音に関する話だけではなく、お節介なサインが無個性で無責任な日本人、につながる話は興味深かった。日本人は物質的に自然を破壊しても観念上の自然は傷つかないから構わない、という指摘は慧眼。2015/10/21
ヒュンフ
1
半分程度読んで終わり。 単純な音の飽和と標語ノイローゼ、垂れ幕などのやかましさに関してはきょうかんできたので読んでみると筆者の言ってる通り彼が一番うるさい この人は暇なのかな。何故他の人は声をあげないと憤慨しているが余暇に差があるからってのが一番の理由 「 交通安全月間らの垂れ幕、あれは免罪符やパフォーマンスの意味しかないように思える 頑張ってるアピール 周囲から見れば暑苦しいが本人は満足気 押し付けがましい感じは日本のウェブデザインとも近い うるささに関しては私個人も日本じゃ浮いてるのかもしれない2019/11/07
キムチ
1
11年前の本。それから時を経て「音の文化」は成熟しただろうか。「一見平和」のこの国のみならずアジア圏はどこも「喧しい」これも文化か・・ 音のみならず文化にはすべてマジョリティ、マイノリティの対立はあるもので、筆者の論法もどうかすると「うるさい」文化論かも。 しかし、政治に阿部氏が復活して、また「美しい日本、誇りある日本」と声高に言われると、確かに音でなく「主張」がうるさく感じる?!2012/09/30