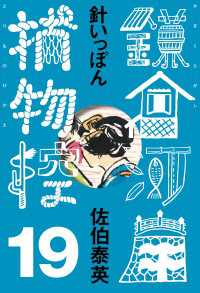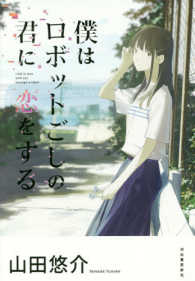内容説明
心理療法をしていて、最近とみに心理的な少年、心理的な老人がふえてきた、と著者はいう。本書は、対人恐怖症や登校拒否症がなぜ急増しているのか、中年クライシスに直面したときどうすればいいのか等、日本人に起こりがちな心の問題を説きながら、これからの日本人の生き方を探る格好の一冊。「大人の精神」に成熟できない日本人の精神病理がくっきり映しだされる。
目次
第1章 日本人の精神病理(母性社会に生きる「永遠の少年」たち;登校拒否症がなぜ急増しているのか ほか)
第2章 ユングと出会う(ユングの心理学;ユング研究所で分析家の資格試験を受ける)
第3章 日本人の深層心理(夢で何が分かるか、何が行われるか;対人恐怖の心理 ほか)
第4章 物語は何を語りかけるか(分析心理学的に読む「浦島」の話;「マザー・グース」と無意識の深層)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kentaro
58
日本人とアメリカ人との間で、公平という言葉の使い方に食い違いがある。日本人は同時に雇った人には公平に同じ給料にしてあると主張するのに対して、アメリカ人は働きの多寡を無視して給料を同じにしているのは、不公平ではないかと主張する。つまり、ここで公平という概念のあり方が両者の間で根本的に違っている。このような違いが生じるのは、筆者が以前から主張しているように、人間の心の中に存在するふたつの原理、すなわち父性原理と母性原理の対立によるものと考えられる。2021/04/09
ころこ
36
エッセイ集だったので、母性の理論的な展開はありませんでした。ヨーロッパ近代化に比べて日本の近代化の劣等性は際立つ。近代化とはどれだけヨーロッパを真似ることが出来るかのゲームだから、それはそうでしょう。しかし、日本の劣等性のことを母性と呼んでいます。当然、フェミニズム的文脈では批判の恰好の材料です。現在のパラダイムでは、母性と父性はそこに一本の線が引かれたときにできる差異なだけで、あらゆる事象をどちらかに分けるゲームでしかないと考えるのではないでしょうか。2021/12/06
昭和っ子
23
「中年とは上昇してきた太陽がこれから下降に向かう時点である。それは下降する事によって充足するというパラドックスを生きる為の出発点である」中年真っ盛りの私に、これから始まるであろうひと仕事を、示唆してくれる。著者がユング派の資格を取る時の顛末を、イニシエイションとして受け止めた言葉に励まされる。「大切な事はこの様なアレンジメントが存在する事。それに関わった人達が渦中において精一杯に自己を主張し、正直に行動する事によってのみ、そこに一つのアレンジメンとが構成されその「意味」を行為を通じて把握しうるという事」2014/02/13
かふ
20
なかなかまとまらないのはそれまで西欧哲学的なものに親しんできたからだろうか。精神分析もどっちかというとフロイト派だったような気がする。ユング派は一見わかりやすいと思うがよく考えるとわからなくなる。それが無意識か。制御できないもの。フロイトが無意識を超自我という意識的なものが克服して独り立ちする父性原理なのに対して、ユングは無意識を対決するものではなく受け入れる母性原理を見出した。漱石が近代自我を問題として、西欧の個人主義に対して東洋の則天去私を見出した。それは西田幾多郎に通じる場の論理。2021/09/29
テツ
18
日本は場の論理に基づき社会が動き、西洋は個の論理に基づき社会が動く(傾向がある) 場を、群れを優先する母性的な社会ではその中から逸脱することさえしなければ大抵のことは許されるけれど、子が自我をもち独立していくことに異常な程の忌避感を抱く。過干渉で過保護的な社会の中で成長しても大人にはなれないよなあ。どちらが良い悪いということはなく全てはバランスの問題なんだろうけれど、個人的には西洋的な価値観の方を好みます。個の意思や感情は群れの平穏無事などよりも遥かに尊い。2021/08/16