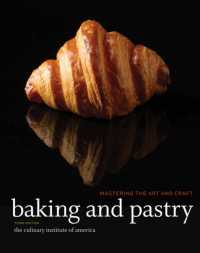内容説明
文豪トルストイ(1828~1910)の処女作。「トルストイへの愛を貫いた」と中野孝次が絶賛した北御門二郎の訳で、感性豊かな文学が甦る。
著者等紹介
トルストイ,レフ・ニコラエヴィッチ[トルストイ,レフニコラエヴィッチ]
1828~1910年。ロシアの作家
北御門二郎[キタミカドジロウ]
1913~2004年。熊本県に生まれる。旧制五高時代にトルストイの『人は何で生きるか』を読み感銘を受ける。東大英文学科を中退。徴兵を拒否して、以来、熊本県水上村にこもり、農業を営みながらトルストイの翻訳に専念する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
syota
34
トルストイが自らの十代前半を振り返って書いた自伝的小説。自尊心が強まり、容姿に劣等感をいだき、「哲学的詮索癖」が著しくなり、周囲との衝突が増えていく。いかにも不器用で扱いにくい子供だけれど、一方で心通い合う友人に巡り合い、思想的影響を受けるなど、作者の精神的バックボーンが形成された時期でもあるようだ。総じて読みやすい反面、トルストイの作品にしては深みや広がりに物足りなさを感じたが、それでもモスクワへの旅の様子を描いた冒頭部などは、緻密で躍動感あふれる描写でさすがの一言だ。2018/09/04
Miyoshi Hirotaka
3
少年時代の始まりは、今まで見てきたいろんな物がくるりと向きを変えて、それまで知らなかった別の面が見えるようになる瞬間。自分が無関心だった人々や自分に無関心だった人々の存在を知り、目の前に果てしない世界が開ける。後になってみれば当たり前のことだが、その当時はそんな風に理解していなかったり、意識していなかったり、はっきりと感じていなかっただけなのだ。自分の態度の他に変わったのは何もない。それだからこそ、すべてが変わった。少年時代は天が与える変化だが、これを自分自身の努力で作り出せる人は永遠の少年だ。2012/05/29
kamome555
2
「12才から14才までの子供、つまり少年時代から青年時代への過渡期にある少年たちは、とくに放火とか殺人とかの犯罪に走りやすいという」そんな時期にある上流社会の少年の、動揺と思索の日々が繊細に綴られています。私にも確かにあった、理由のない負の衝動に負けそうになる不安定な時期を思い出しました。男の子の方がさらにこじれていそう、何となく。2014/03/08
鮎川玲治
2
こういう小説をこんな読み方をしていいのかは知らないが、自分の子供の頃と重ね合わせて「ああ、そうそうそんな感じ」とじたばたしたくなる箇所がそこかしこにある。19世紀のロシアであれ20〜21世紀の日本であれ、子供の成長期なんてそんなもの、なのかもしれない。2013/03/02
-

- 和書
- 韓国学ハンマダン
-
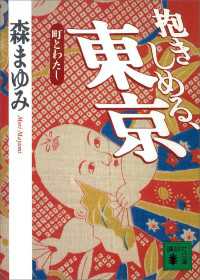
- 電子書籍
- 抱きしめる、東京 町とわたし 講談社文庫