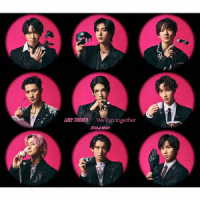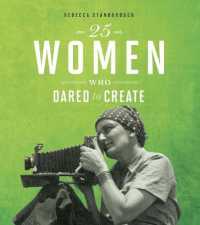内容説明
殿中の煩雑な儀式の最中に尿意をもよおした大名はいったいどうすればいいか?誰も教えてはくれない疑問に「柳営学」はこたえてくれる。江戸学の泰斗、三田村鳶魚の晩年に侍し、その最後の教えを受けた著者ならではの縦横の筆が活写する千代田の城中。併せて師の最晩年の姿を語る貴重な証言「この本はおまえさんに譲ってやろう」を収録。
目次
第1話 江戸城のトイレ、将軍のおまる
第2話 「それへ」は公方様のマジックワード
第3話 大名行列を見分けるコツ教えます
第4話 格付けにこだわる大名たち
第5話 官位と席次は悩みのタネ
第6話 殿中不作法
第7話 柳営とは練習と挨拶と見つけたり
第8話 この本はおまえさんに譲ってやろう
著者等紹介
小川恭一[オガワキョウイチ]
1925年生まれ。東京出身。1943年、慶應義塾大学の学生当時、奥野信太郎教授の紹介により三田村鳶魚翁を中野文園町に訪問、師事し、翁より処分寸前の貴重な柳営関係の記録・写本類の譲渡を受ける。上野の帝国図書館に数年勤務の後、目的を中断して戦後長らくサラリーマン生活を続けるが、ふたたび研究の道に入り、大名・旗本・御家人を中心とする徳川幕府制度の実態を明らかにする。2007年9月25日逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
113
古代支那において、将軍の幕舎は柳の木をフレームとしていたため、幕府のことを「柳営」と洒落た言い方をしているのである。『トリビアの泉』で公用朝夕人で取り上げられて、随分懐かしさを覚えた。…それは兎も角、著者は江戸学の泰斗三田村鳶魚の最後の弟子に当たる柳営学の権威者である。が、会話体と論説文で構成される文章は無学な六点にとっても読みやすいものであった。そこから出てくる大名の生活とは繁文縟礼、極めて複雑なものである。儀式は予行演習が欠かせず、古手の大名は人気講師的な面もあったりね。凄まじきものは宮仕えであるよ。2023/03/16
ウッチー
6
「柳営学」という分野を始めて知った。城内のしきたりや順序、決まり事など当時も大変であったと感じたが、やはりなかなかベールに包まれわからないことが多い将軍の「尿包」(しとつつ)や黒い「おまる」の話が印象的であった。2015/07/02
伊達者
5
柳営学という分野の本。例えば大名が江戸城における振る舞いを他の大名から何度も教えてもらわないと大変だとか。儀式の予行演習をするというのが面白い。大名が畳に躓いただけでいわば進退伺を幕府に文書で出し、お構いなしと文書で通知したとか。というのには大笑いしてしまった。大名もつらい仕事だが、陰で補佐する留守居役が大活躍するのは現代の総務部長と同じ。日本の組織風土は江戸時代から引き続ている。2023/02/10
takao
2
ふむ2023/01/16
武隈
0
江戸城のトイレ事情だけてなく、今まで読んだ江戸時代の紹介本よりしきたり等江戸幕府の仕組みが詳しく良く判ります。興味深く読みました。2015/12/29
-
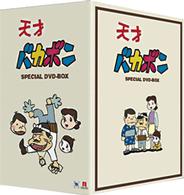
- DVD
- 天才バカボン DVD-BOX