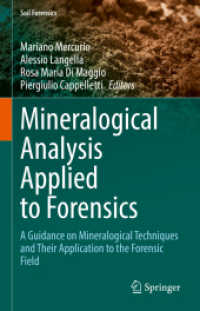内容説明
明治十五年、近在屈指の大地主の長男として生まれ、九歳の時母自殺。以降徐々に家は没落、時代の傾斜と並ぶようにやがて不幸の淵に沈んでゆく。大正十四年出家。大正十五年四月、解くすべもない惑ひを背負うて、行乞流転の旅に出た。分け入つても分け入つても青い山(「俳句」大正十五年)九州から東北まで漂泊托鉢。行乞生活を記録した句は数奇な生涯を凝縮。俳句、随筆、行乞記の三章でその真髄を纏める。
目次
俳句
随筆(初期随筆;出家以後)
行乞記 抄
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
54
俳句、随筆、旅日記「行乞記」を収録。著者の書いた文章を読むたびに「放下」という言葉が思い浮かぶのだが、「行乞記」を読むとまさにそれ。西行から芭蕉へと続く漂泊の文人の末裔という気がするなあ。彼らと違い生活苦みたいなのも見て取れるけど。あと随筆を読んでいると若いころは理に走っているが、だんだんとそれが磨かれて一切から離れた境地に至るのも読む方もまた心地よい。出家以前と以後に顕著。ただやはり一番は俳句。何度も読んだはずの句を転がすようにしてまた味わった。「松はみな枝垂れて南無観世音」「生死の中の雪ふりしきる」2020/09/13
Y2K☮
38
ボブ・ディラン「ライク・ア・ローリングストーン」とビートルズ「アイ・ミー・マイン」を混ぜて実体化した漂泊の俳人。托鉢しながらの旅なのに酒と煙草はやめる気ゼロだし「宿の食事がまずい」「風呂に入りたい」「道を教えてくれないなんて不親切」など愚痴のオンパレード(笑) 職を転々とした苦労人なのにどこか天真爛漫なのは、大地主の家に育ったゆえか。家族も社会生活も捨てて句作に生きたピュアな男だが、反面教師と憧れが半々かな。好きな句は「あてもなく踏み歩く草はみな枯れたり」「ふくろうはふくろうでわたしはわたしでねむれない」2015/08/04
Sakie
14
引き続き山頭火。焼き捨てた以降の日記や、「三八九」などに掲載した随筆を集めたもの。随筆は真面目に論じよう、努めて前向きになろうとする気配が無理っぽくてしんどい。かといって泥酔、乱行や不義理の自省と言い訳も度重なればうんざりする。働いて稼がずに生きる世過ぎが、そもそも私には理解しがたい。貧しい人にいただいた喜捨を、いい宿や酒に費やす是非やいかん。と眉をひそめたところで、こちらだって読みながら呑む酒が過ぎており、人のことを言えた義理じゃない。『ほろほろ酔うて木の葉ふる』。風流ではない。この降り積もる苦さよ。2024/04/14
あなた
8
山頭火にとっての問題は、俳句という表象をどれぐらいそぎおとせるかということにあった。主体も客体もなく、風景もふちどらず、文学理論や文学モードに折半されず、みずからの意志や欲望にも容喙されず、そいでそいでそぎおとしたところに「まつすぐな道でさみしい」が出てくる。随筆を読むと、みずから哲学を体系化しているし、またえらく感傷的でチープな思想や警句が散見されるけれど、それを放浪することでそぎおとしたところに「山頭火」という記号システムをつくる契機があった。2009/08/14
Nepenthes
1
しみじみと良い。ただただ、ひたすらに良い。近代社会になる以前の日本の自然、文化、人々の暮らし、そして山頭火の心象風景が朝露のような清廉さで描かれている。何か気持ちが落ち着かない時に本書を手に取ると、心が洗われて真に良い生活を送りたい気持ちになり、身も心もきりっとする。夜はラーメンでも食べようかなと思っていたところが、きちんとした一汁一菜になる。そんな一冊。これは手放せない。2021/11/05