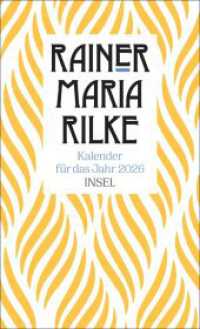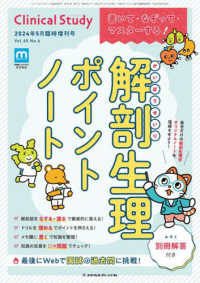内容説明
「日本浪曼派」は神保光太郎、亀井勝一郎、中島栄次郎、中谷孝雄、緒方隆士、保田与重郎ら六人で創刊した雑誌名であるが、戦前、大日本帝国の侵略的アジア主義、満州国の擁立から第二次世界大戦の流れのなかで文学運動をこえて、青少年に思想的に多大な影響を与えた。本書は、日本浪曼派の中心人物たる保田与重郎らの近代批判、古代賛歌的日本主義などを初めて精細に批判、検証したもの。
目次
1 日本浪曼派批判序説(問題の提起;日本浪曼派の問題点;日本浪曼派の背景 ほか)
2 停滞と挫折を超えるもの(世代論の背景;実感・抵抗・リアリティ;今日の文芸復興 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しゅん
16
1960年刊のデビュー作。日本浪曼派とは即ち保田與重郎のことであり、著者はその保田の思想にイカれた自らの青春を相対化する。日本人は西洋人のように宗教観念に対して自身を犠牲にすることはない。しかし、「美」に対しては喜んで身を捧げる。保田の国粋主義は「政治における美意識の全面化」であり、閉塞状態における「美」への信頼こそがファシズムの根源であるという議論は説得的かつ現代的。本論の他に保田と太宰の比較、橋川のひと世代下にあたる大江と石原に対する批判的言及など、時事的ながら今読んでも興味深い批評も含まれています。2019/02/24
oz
10
初読。保田與重郎というカリスマによって戦中の一時期に隆盛した日本浪漫派。危機的な時局を肯定し、古典礼賛と皇国賛美を繰り返したとして戦後封殺されたが、保田自身は当時の若者の熱狂的支持と裏腹に、右翼からも転向文学者からも敬遠されるほど政治的リアリズムから乖離した文学論を展開していた。戦時中の日本は西洋的なファシズム体制ではなかったが、本書は保田與重郎の(カント的な意味での)批判的読みを通して、実は戦時下に現れた死への誘引、非政治的陶酔といった「日本的ファシズム」への鋭い分析になっているのに驚くばかり。2018/05/27
COPPERFIELD
8
日本浪漫派批判序説 P109 美と政治とが全く異なる価値領域に属することは断るまでもないだろう。それはその実現の場において異なるばかりでなく、その成立する理由に関しても異質である。美と政治とは、関係がないと言う意味でしか関わりをもたない、二つのカテゴリーにあると考えられるほかないである。 しかし、わが国の精神風土に置いて、美がいかにも不思議な、むしろ越権的な役割をさえはたしてきたことは、少しく日本の思想史の内面に目をそそぐならば、誰しも明らかにみて取ることができる事実である。 2013/11/09
ぽん教授(非実在系)
7
日本浪漫派、とくに保田与重郎を中心に批判を試みた書。単なる戦犯としてではなく、拠って立つ根拠を一つ一つ解きほぐして逐次批判していっており、その意味では社会科学的。しかし著者が一回日本浪漫派にハマった戦中派であり非常に自罰的であるように、心の弱さを持つ人が入り込みやすいものをなんとか反戦平和を最終的な根拠にして批判していて、著者は死ぬまでこれをもとに弱弱しく立ち続けるしかなかった。保田与重郎に勝ったつもりになっていたのである。2017/09/05
左手爆弾
7
具体的な文学史の知識、あるいは当時の空気についての実感がないと理解するのは難しい。それでも、啄木が記す「何か面白いことはねぇかな」という退屈の中での苛立ちが、日本浪漫派の「私達は死なねばならぬ」という熱狂へ繋がる見通しは比較的得やすい。具体的状況や現実は成立した瞬間に歴史として美化され、正当化される(現実—歴史—美の一体化:114頁)。小林秀雄がジイドらと比べて日本の私小説は「私と世界が一体化している」と指摘していることは非常に興味深い。要するに、セカイ系と言われているものは日本浪漫派なのではないか。2015/06/11