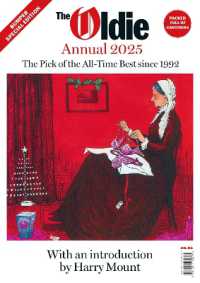内容説明
贋の権威や通俗の価値に決して近寄らず、小走りせず、あくまで自分の文学の“背骨”をひたむきに創りつづけた日本の“親爺”木山捷平の最晩年の味わい深い短篇群。敬愛してやまぬ井伏鱒二の秀逸な素描、若き太宰の風貌等、市井の人として生き通した文学者の豊かで暖かな人生世界。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ただいま蔵書整理中の18歳女子大生そっくりおじさん・寺
71
木山捷平最晩年の短編集に井伏鱒二と太宰治の回想記が付いた一冊。やっぱり私は捷平が好きである。巻頭を飾るのは『骨さがし』という短編だが、まず捷平さんが自炊を始めた頃の話からスタート。しかし次第に面倒になり、日中から飲酒する。他の私小説家ならこれで人間が堕落してゆく1本の短編を作るだろう。しかし我らの木山捷平は自炊(立志)から飲酒(堕落)までわずか1ページである(笑)。そこから遺骨を探すハメになり、「で、何の話だっけ?」(©️高田純次)状態にさせられる。木山捷平には軽みと同時に良い速度がある。これもお薦め。2019/09/04
軍縮地球市民shinshin
9
木山捷平晩年の短編を集めた文庫。特に「弥次郎兵衛」・「釘」が良い。本当にどうでもよい日常の些事を書き綴った小説だが、深夜にひとり読書しているとなぜか沁みるものがある。技巧的な小説よりもこっちのほうがいい。2017/10/22
あなた
8
太宰との交遊記があるが、上林暁もつるんでいたり、あと津村信夫も加わっていた同人話などもあって勉強になった。太宰は長い校正をする人間であったこと。木山から受験参考書用の高校生のための西鶴を借りていって「新釈諸国噺」を書いたこと(西鶴が雅俗の攪乱者であったように太宰はメディアの階層を破砕する)。太宰が六男坊の文学で、志賀が長男の文学だというのはうまいね。わろうた2009/08/25
アメヲトコ
6
今年100冊目。知人からいただいた本で知った木山捷平、飄々とした文体にえも言われぬ味わいがあってやはり好きです。「赤い提灯」「弁当」などにはほのかな色気も。「太宰治」は若き日の太宰の姿や名作「津軽」が生まれたときのエピソードなど、意外な一面が垣間見られます。2018/08/03
eazy
4
「骨さがし」と「赤い提灯」がよかった。 絶妙。2002/06/17