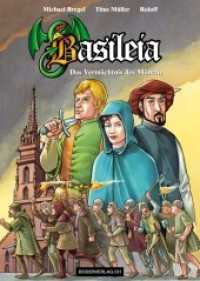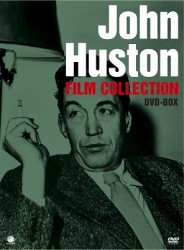内容説明
世を避けて隠れ忍ぶ村里―かくれ里。吉野・葛城・伊賀・越前・滋賀・美濃などの山河風物を訪ね、美と神秘の漲溢した深い木立に分け入り、自然が語りかける言葉を聞き、日本の古い歴史、伝承、習俗を伝える。閑寂な山里、村人たちに守られ続ける美術品との邂逅。能・絵画・陶器等に造詣深い著者が名文で迫る紀行エッセイ。
目次
油日の古面
油日から櫟野へ
宇陀の大蔵寺
薬草のふる里
石の寺
桜の寺
吉野の川上
石をたずねて
金勝山をめぐって
山国の火祭
滝の畑
木地師の村
丹生都比売神社
長滝白山神社
湖北菅浦
西岩倉の金蔵寺
山村の円照寺
花をたずねて
久々利の里
田原の古道
越前平泉寺
葛川明王院
葛城のあたり
葛城から吉野へ
1 ~ 3件/全3件
-

- 電子書籍
- かくりよの宿飯 あやかしお宿に嫁入りし…