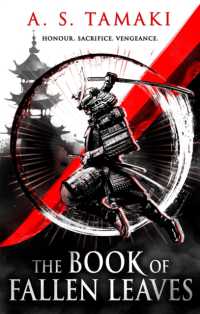内容説明
『芸術的抵抗と挫折』『抒情の論理』の初期2著からユダヤ教に対する原始キリスト教の憎悪のパトスと反逆の倫理を追求した出世作「マチウ書試論」、非転向神話をつき崩し“転向”概念の根源的変換のきっかけとなった秀作「転向論」、最初期の詩論「エリアンの手記と詩」など敗戦後社会通念への深甚な違和を出発点に飛翔した吉本降明初期代表的エッセイ13篇を収録。
目次
恋唄
エリアンの手記と詩
異神
マチウ書試論
西行小論
宗祇論
蕪村詩のイデオロギイ
鮎川信夫論
戦後詩人論
芥川龍之介の死
芸術的抵抗と挫折
転向論
戦後文学は何処へ行ったか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
40
『マチウ書試論』-ドストエフスキーのところまできて、色々調べてみました。すると、マチウとはマタイのことで、ジェジュとはイエス、ジャンとはヨハネのことだというじゃないですか。そこまで原始キリスト教の何かに関わる文書だと思って読んできましたが、迷宮は殆どスタートの位置と変わらないところに出口があった。だまされた~とも思いましたが、固定観念に囚われず、その聖典を曇りのない眼で読む批評的な態度を試されていると文意を理解することもできます。全く知らない者へこそ、優れた読書体験が贈与される不思議な文章です。2019/05/07
逆丸カツハ
39
関係と情報の哲学と銘打った本を出版した自分にとって、「関係の絶対性」を唱える本書は避けてはならないものだったのだが、なんか吉本隆明って言ってることを真に受けてはいけない人な気がして、手にとって来なかった。読んでみたら、まあ、あながちその予感は外れではなかったかもという感じである。そして、どちらかというと関係の絶対性を提唱した「マチウ書試論」よりも転向の精神性を分析している部分や詩のほうが興味深く、面白かった。2025/11/18
あや
28
転向論読みたさに買う。転向文学と言えば中野重治。予想以上に中野重治「村の家」の引用部分が多い。転向しても筆を折らずにその時の心情を描き続けた中野重治の「村の家」は今の時代に読まれてほしい短編で中公文庫や講談社文芸文庫のKindleで読めます。転向論の冒頭出てくる本多秋五さんのご著書も読んでおきたい。文学が戦争に加担しそうになる現代、転向文学や文学者の戦争責任など、多くの方に考察されてほしいと思っております。2025/05/22
かふ
18
吉本隆明の初期評論集。「エリアンの手記と詩」はなんかセンチメンタルで恥ずかしくなるのだが吉本隆明も最初は青かった(初々しいとも)。「マチウ書試論」も「マタイ伝」をフランス語読みで書く理由が衒学的でよくわからない。ただフィクション性という「でっち上げ」の宗教論。第二章がドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』の「大審問官」でのイエスと悪魔の対話を論じ、イエスが取った立場の絶対的な信仰(神の秘跡を許さない、それは神を試すことになるから)とニーチェの『善悪の彼岸』(奴隷の宗教)との相対化。 2020/08/05
しゅん
17
十数年ぶりの再読。3つの詩と10の批評を収めた初期選集は、そのまどろっこしい書き方の中に、構造への着目を宿す。泥沼の戦争を可能にした日本社会秩序は侮り難く、封建制と近代化が互いを支え合う構造を読み解かない限り、詩人も文学者も転向者も力を持たない。感情を構造と重ねて捉えること。それが、吉本が中野重治やマチウ(マタイ)書を論じるときの方法であり、詩を書き始めるための支点ではないか。「関係の絶対性」とは、すなわち構造化した感情のことではないかと思われる。2022/04/18