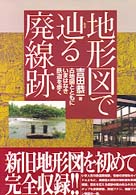内容説明
近世初期、武家社会で流行した殉死。それは主君に対する忠誠心の発露とされ、美談や悲劇として語られる。だが戦国時代、主君を犠牲にしても助かろうとした武士が、なぜそのような行動をとるようになったのか。森鴎外が小説『阿部一族』に描いた事件を契機に、細川家・伊達家の殉死者の経歴や行動を史料から丹念に辿り、武士の心情に迫る。独特の日本文化に潜んだ意外な本質とは。
目次
プロローグ 殉死と忠誠心
1 阿部一族の悲劇
2 情死としての殉死
3 細川忠利の殉死者
4 細川忠興と光向の殉死者
5 伊達政宗の殉死者
6 下層の殉死者たち
7 殉死者とかぶき者
8 「忠臣蔵」の本質
9 武士道の成立事情
エピローグ 殉死解釈にみる死生観の転換
著者等紹介
山本博文[ヤマモトヒロフミ]
1957年生まれ。東京大学文学部国史学科卒業、同大大学院人文科学研究科修士課程修了。現在、東京大学史料編纂所教授。文学博士。専攻は、日本近世史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
金吾
22
忠義心というより一体感や武士の一分を求めて殉死をしたという話は理解しやすい話でした。また恩は恵まれない立場の人の方が些細な事でも感じるのだろうなあと思いました。2025/02/06
駒場
3
「阿部一族」などで得た殉死観を持っている人に勧めたい一冊。江戸初期~元禄期の殉死を、殉死者の大半を占めていた中級~下級武士を特に注意深く述べることで考察していく。主君への愛情表現、一方的な主君との一体感(という幻想)の体現、自己のアイデンティティの表現方法であった殉死が禁止されることで、それまであった『忠義』が姿を消す。そして生まれた武士道書は「恩」を語るが太平の世の武士達には響かない。寧ろ藩という「世間」の中での処世術を求めるようになる。ここに「世間」の萌芽が見られるあたりが、面白かった。2011/07/05
半木 糺
2
森鴎外の『阿部一族』で描かれている殉死は封建的で非人間的なものとなっているが、本書で示される殉死観はそれとは様相を異にする。著者は殉死をしている人物がその家代々の譜代の臣ではなく、むしろ新規召抱えの家臣が多いことに着目。殉死は彼らの「傾いた」行動であり、自分を取り立ててくれた主君への個人的な繋がり、一体感を求めるものであったのだ、としている。この結論は近世初期の武士の心性を見る上での重要な視座になりうるであろう。2011/10/08
杞人
2
「つまり、恋愛感情に近い形で主君を思うことや、武士としてのアイデンティティを保とうとする心の動きこそが、それまでの忠誠心の本質であったと思われる。(中略)それ以外に『渡り者』たる武士の忠誠などどこにもないのである」戦国の余韻の残る江戸初期の武士たちは恐るべき超武闘派ナルシストであり、自分や他人の生命は元より、朋輩や主君への没我的犠牲心の発露さえその表現手段の一つに他ならない。軽輩の身ながら一度親しく言葉を賜ったことを理由に殉死を敢行するとは、まるで恋に恋する乙女のようだ。…まあ結果はシグルイですけどね。2011/06/16
guanben
0
面子、面目、世間体。武士の殉死も極めて日本的な理由から。それでハラキリしちゃうのも凄いけど。2016/06/30


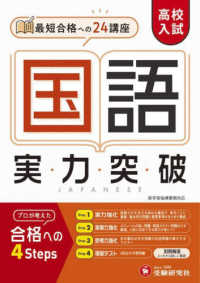
![とく問カードジュニア 小学4年英語 [レジャー]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/49099/4909961240.jpg)