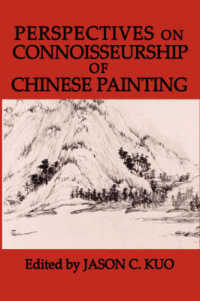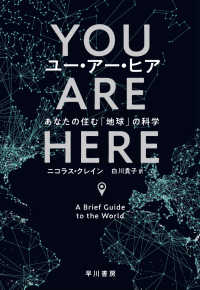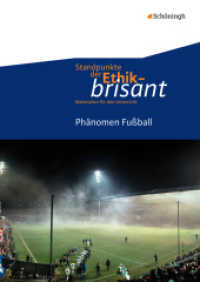出版社内容情報
法学・哲学の出会いと学問としての可能性。非常識の世界に属する哲学と常識の世界に属する法学の共闘はいかなる問題解決に有効なのか正義の根拠とは? 法の拘束力とは?
法学と哲学の逆説的関係から生まれる根本問題に挑戦
知の愛である哲学が非常識の世界に属するのに対し法学は常識の世界に属する。両者の出合うところ人間存在の根源的問題が立ち上がる。世界を支配する理性が社会において自然法として現れ、個人の内にも浸透し秩序を齎(もたら)すという順接的関係が疑われるところに生まれる諸問題。正義の根拠、人間性と社会秩序、法と実力など、法哲学の論点を易しく解説。
A:赤信号だ。渡るのはよせ。
B:いや轢かれて死ぬのは俺だ。放っておいてくれ。
ここでAが何と答えても、それは倫理学・法哲学上の1つの立場といいうる。例えば「ああそうか、じゃ勝手に死ね」「馬鹿をいえ、轢いた運転手やら、後続車やら、みんな大迷惑だ」「死ぬのはお前の勝手だが、法律を破るのはお前の勝手じゃないよ」「生命あっての物種じゃないか」 このように、私たちは、日常生活においても、もろもろの法哲学的問題に取り巻かれて暮らしている。――<本書より>
第1章 法哲学とは何か
第2章 人間性と法
第3章 法とは何か
第4章 実定法
第5章 実定法を超えて
第6章 法哲学と現代世界
長尾 龍一[ナガオ リュウイチ]
著・文・その他
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
takeapple
18
法哲学が面白いのか、この著者である長尾先生が面白いのか、おそらくその両方だと思うが、結構難解な内容をシニカルに分かり易い例え(きっと今の30代以下には通じないかも)を用いて表現している。古代ギリシャから古代中国まで幅広い哲学的素養が面白いと感じる一番の源かな。学生時代の教養科目の哲学を担当していたギリシャ哲学が専門の武井先生を思い出した。2020/10/22
ヤギ郎
14
読み始めてはやめ、その繰り返しでなかなか読了できなかった一冊。法哲学入門と題されているが、法や哲学そのものを問いていく良書である。著者はケルゼンを専門に研究した大家であるが、専門にとらわれず幅広い文献から法哲学を考察している。著者の知識量と文才に圧倒される。法学者は時に「屁理屈ばかりいう迷惑なヤツ」と思われているが(間違いではないのだが…)、法学者が緻密な議論の中で構築しようと社会を本書から感じ取りたい。講義レベルの法哲学は教科書を参照して欲しい。2020/08/28
袖崎いたる
13
冒頭にあるように、法哲学は三者三様の学問であるらしく、読後にその言葉に戻っても違和感はない。この違和感のなさを受けて、この本の印象を<法哲学>入門ではなく、<長尾龍一>入門と読み換えてもいいだろう。それと、法設計のモデルとなるべき人間が、「正義のために行動し、他人の欠点よりも長所を取り上げる人物」という孔子の説く君子的人物ではなく、人倫に対して可謬的な小人物であるという発想は、現代的でもあり、古くは中国の韓非子も考えていたらしい。これって現代に、「動物化」という語で論じられている人間論の発想と同じだろう。2015/11/13
masawo
12
「法⇔人間の本性」にフォーカスしつつ、旧き良き教養に裏付けられた古今東西の小噺をこれでもかとばかりに放り込んでくるが、結果的に法律の成り立ちや解釈、問題点などについて腑に落ちる感があるので入門書として極めて優秀。著者の授業を受けてみたくなる。2022/02/25
りん
11
法学教室の新連載「基礎法学のススメ」の冒頭で「ニュアンスや程度の差こそあれ、基礎法学の研究者が怖いという実定法学者は多いだろうと推測します…しかし基礎法学がなぜかくも恐れられるのか。それは一言で言えば「逃げない」点にあるように思います。」とあったが本書を読むと確かにそんな感じがする。現状に対するブラックでシニカルな表現が多々出てくるが、それも「強度の知的な廉直さ」ゆえなのだろうし、誤魔化しや追認的解釈に頼らない法哲学的な見方も法と社会の発展には必要なのではないかと思わせてくれる良書。2018/09/09