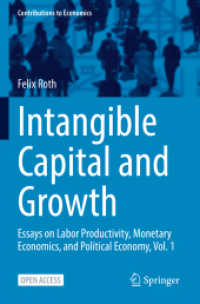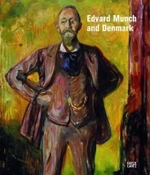内容説明
東京は、天下の総城下町から、一挙に近代国家の首都へと移行したのではない。その過渡期は明治前半期であり、東京が「東亰」とも呼ばれた時代であった。それは、文明開化の時流に取り残された江戸根生いの民が、江戸文化の名残を引きずりつつ生きた時代でもある。江戸から東京へと変貌していく過程を生きた、市井の民の生活実態を浮き彫りにする。
目次
序章 変革の嵐
第1章 「文明開化」の幻影
第2章 暮らしの曲線
第3章 開化の蔭で
第4章 庶民の遊び
第5章 寺子屋始末記
終章 東亰時代
著者等紹介
小木新造[オギシンゾウ]
1924年、東京生まれ。東京教育大学文学部日本史学科卒業。日本文化史専攻。文学博士。桐朋学園大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みつか
7
「上からは明治などといふけれど、治明(おさまるめい)と下からは読む」このころの狂歌である。 文明開化の気運がたかまり、それを揶揄してきっと民草はタカアンドトシおなじく「欧米か」ってツっこんだことでしょう(笑) 江戸っこにとっては、徳川さまの方が住みよい時代だったのかもしれません。本書は維新まもない東京の街の庶民の暮らしぶりを衣食住、結婚、遊び、私塾などの学び、湯屋、洋医と漢医等幅広く教えてくれます なかでも「火事と喧嘩は江戸の華」といわれるように 火事について多くのページをさいています。2019/05/28
katashin86
2
今ではまったく使われない、京の異字「亰」が用いられた江戸東京の過渡期の諸相をつづった一冊。江戸期の美質を失いつつ近代都市へ変貌していく東京の姿は、初版1980年当時の、バブルの狂騒・乱開発のいよいよ進む世相の批判でもあったのだろう。2024/08/03
ゐ こんかにぺ
0
サブタイトルにもあるとおり、「江戸」と「東京」の「間」の時代の一般市民の生活を扱っている。速やかに「東京」になりたい政府と、「江戸」のままのつもりでいる市民のずれから起こる、「東亰」の中身が面白かった。2012/01/26
-

- 和書
- 自治六法 〈令和7年版〉