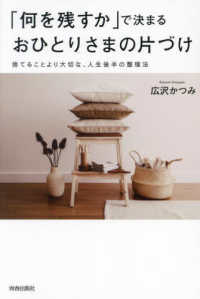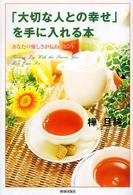内容説明
フッサールとハイデガーに現象学を学び、フランスに帰化したユダヤ人哲学者レヴィナス。戦争の世紀の証人として生き、「平和とは何か」の問いを極限まで考察したレヴィナスは、本書において他者への責任とは他者の身代りになることだと説く。『存在と時間』(ハイデガー)以降最も重大な著作とされ、独自の「他者の思想」の到達点を示す大著の文庫化成る。
目次
第1章 存在することと内存在性からの超脱
第2章 志向性から感受することへ
第3章 感受性と近さ
第4章 身代わり
第5章 主体性と無限
第6章 外へ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
テツ
30
哲学は個人的な体験というフィルターを通さなければ熟成されない。親族のほぼ全てを収容所で殺害されたレヴィナスの哲学を、彼の言葉を、平和な時代の平和な島国で生きている僕が真の意味で理解することなんて出来ない。それでも彼の語りたいこと、彼が美しいと感じ、人間誰しもが普遍的にもつ(と信じたかったであろう)感覚が僕も好きだなと思う。いくら踏み躙られた経験があろうとも愛も神も信じたい。美しいものとして存在していて欲しい。人間に寄り添っていて欲しい。そのために言葉を積み重ねる。2019/06/28
きゃんたか
22
レヴィナスは確信犯的に自我中心的な西欧哲学の転覆を意図している。感受性を備えた身体性によって知性の限界を、起源の想起不能性を以て人間存在の徹底的な受動性を主張するという様に。時間には乗り越えられない隔たりがあり、総合によって共時化を図る知性において、ロゴスは挫折せざるを得ない。ロゴスは常にかかる身体の超越を記述の痕跡をもって裏切る定めにあるが、著者はそれさえ承知の上で語り直しの反抗をやめようとしない。かかる自己の脱措定による社会正義の可能性、宗教抜きにかかる倫理が有り得るのか、残された課題はこの二点だ。2017/07/21
∃.狂茶党
17
* とりあえず読み始め。 別の何かという、捉えどころのない、捉えた瞬間に別のということがすり抜けてしまうものについての、めんどくさい考えから始まる。 フッサールに比べればわかりやすいものの、かなり難解。 それというのも、言葉の壁の向こうにあるもの、認識することの向こうにあるものを認識し考えようって、無理筋の試みを行なってるからだと思われる。 2023/06/21
内島菫
10
本書では、他者が死に比せられているようにみえる。どちらも、私が能動的に引き受けるよりも前に私に負わされた受動的な受動性であり、一方的に負わされるものであり、彼性の顔であり、にもかかわらず(むしろだからこそ)近さにおいて意味を持ち、その意味とは責任である。不安や恐れという一般的な死のイメージが、自我の家に閉じこもっていられるだけの余裕のあるものに思えてくる。ハイデガーが存在論の勝者のようにあるならば、レヴィナスは存在論での負け戦を、言葉から誤用である「正しさ」を抜き取り、果敢に闘っているようでもある。2014/01/09
K
9
レヴィナスやっぱり難しい。『全体性と無限』の方がまだ入って来た気がする。とはいえ、語ること・語られるものという相互性の破壊、従来の存在論への批判、フッサール、ハイデガーからの継承、近さ・責任・身代りという概念など所々良く分かるところもある。一言で言えば、我を超えた存在から、存在の彼方から、語り得ないものから、無起源的なものから全てが始まるということを言いたいのだと思う。語りえないものを、どうしても言語を使用して語らなければならないという越えがたい問題を抱えつつ、慎重に、時にダイナミックに示す試みである。2025/08/15
-

- 和書
- 数理統計学ハンドブック