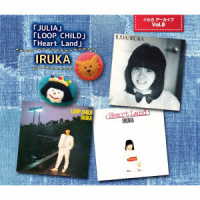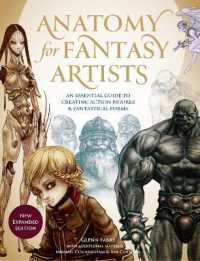出版社内容情報
【内容紹介】
人の住む近くにはものやたま(スピリットやデーモン)がひそむ。家や土地につくそれら悪いものを鎮めるために主は客神(まれびと)の力を借りる。客神至れば宴が設えられ、主が謡えば神が舞う。藝能の始まり。著者は、時を遡って日本藝能発生の直の場面に立ち合おうとするかのようだ。表題作「六講」に加えて名編「翁の発生」を収録。著者の提示する「発生学風」の方法こそ近代学問の限界を突破する豊穰なエクリチュール。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
∃.狂茶党
18
折口信夫による語り。 講義をまとめたもので、書き綴られたものではないが、その分読みやすい。 けど、話の道筋は、ちょっとわかりにくい。 記録が残らぬ始原まで遡ろうとしているから、わかりにくくて当たり前。2024/06/06
roughfractus02
7
芸能を目的を持ち見物人を集める催事と考える現代に対し、著者はそのプロトタイプを「まつり」に見て発生的に捉え、自然への願いや鎮魂の際、踊りは主(あるじ)が客(まれびと)を饗応し背かぬように地を踏み鳴らし舞って迎えることが継承され芸能となったと仮説する。シャーマニズム的行為としての踊りは「外からよい魂を迎へて人間の身体中に鎮定させる最初の形」であり、魂の遊離時に体の変調を防ぐことも含め、田遊び、田楽、猿楽、歌舞伎に辿り、能、相撲、盆踊り、伊勢踊り、踊り念仏等様々な形となった、と本書は予想する。(1941年刊)2025/03/21
うえ
7
「まれびとなるものの実際は、別に何処から来た訳ではありません。やはり、其村人であつたに違ひありません。唯さういふもののやうな形で出て来て、そのやうな手ぶりをするだけです。だからやはり普通の人間です」「南信州の一部分は、私も歩いて来て、此地方にある田楽の、輪郭だけは、思ひ浮かべる事ができます。此は北遠州天竜沿ひの山間にもある事は、早川孝太郎さんの採訪によって知れました。種目が可なり多く具はつて居て、田楽と称する土地の外は「花祭り」と称へてゐて、明らかに田楽の特質の一部を保つています」2017/11/06
GEO(ジオ)
5
読了。再読みたいだが、読んだ記憶が全くない(汗 それはともかく、民俗学の碩学として知られる折口信夫による、「日本芸能史」の講義をもとに、書籍化したもの。 このほかに「翁の発生」など、折口信夫の芸能に関する論考を一緒に収録。 旧仮名遣いで書かれており、多少読みにくいところもあるが、面白い内容だった。民俗学・文化人類学が好きな人は読んでみるといいかも。2016/07/04
tyfk
4
能の翁のことを知りたく『翁の発生』収録の本書を。翁の語り、翁の宣明、もどきの所作、翁のもどき。磯崎新の「始源のもどき」論は、折口信夫の論に依拠したものらしい。 2023/07/23
-
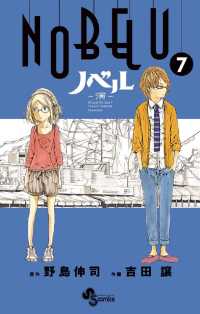
- 電子書籍
- NOBELU-演-(7) 少年サンデー…