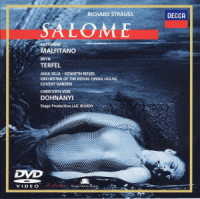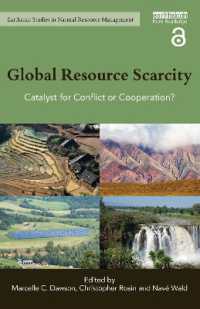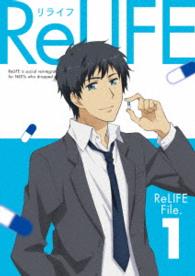内容説明
マルクス=ヘーゲル主義の終焉において、われわれは始めてマルクスを読みうる時代に入った。マルクスは、まさにヘーゲルのいう「歴史の終焉」のあとの思想家だったからだ。マルクスの「可能性の中心」を支配的な中心を解体する差異性・外部性に見出す本痛は、今後読まれるべきマルクスを先駆的に提示している。価値形態論において「まだ思惟されていないもの」を読み思想界に新たな地平を拓いた衝撃の書。亀井勝一郎賞受賞。
目次
1 マルクスその可能性の中心
2 歴史について―武田泰淳
3 階級について―漱石試論1
4 文学について―漱石試論2
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
oz
28
再読。価値は商品に固有のものではなく、他の商品との関係において成り立つ。価値を担保する中心(貨幣)の措定はその関係を隠蔽して、あたかも商品自身に固有の価値があるかのように認識させる。この構図は哲学上の自己、物理学上の数学といった形而上学全般に敷衍できる。全ては形成された共同主観性でしかなく、反省や自己批判はこの中でなされる限り必ず失敗する。可能性の中心を探るとは、全てが見渡せる場所に立つ事ではなく、その足元すら失って宙吊りになる所まで自らを移動させる困難な行為に身を投じることである。柄谷思想の白眉。2014/05/04
ころこ
26
本書では、たびたびソシュールが引用されています。構造主義としてマルクスを読み替えるアイデアは、アルチュセールから日本に輸入され、その実践として本書はあるようにみえます。「ソシュールは、言語を価値形態としてとらえることで、「意味」を破壊した。」(P63)著者は、「あとがき」にある通り、自分は漱石だろうがマルクスだろうが、何かを考えることのきっかけに過ぎないといっています。他方、漱石やマルクスに、なぜか回帰してしまう力がそこにはあるともいっています。著者が『意味という病』から引き続いて、意味や価値の問題にこだ2018/05/21
chanvesa
26
言語学からのアプローチであったり、微小な際から固有性を見出だす。このような緻密な方法は読んでいてただただ驚かされる。理解が覚束ない。論理の飛翔が鮮やかに着地するが、どうやったらそのような軌跡を描けるかよくわからなくなってくる。漱石試論や泰淳論も同じ。可能性の中心を読むという手法。先日、恩師にも精神現象学を読むことについて同様のことを言われた。専門家じゃないんだから何をつかみ取れるか。2015/10/24
こうすけ
22
うんうん言いながら、一生懸命読みました。『資本論』をもとに、経済学をこえてマルクスの思想に迫る。漱石論なども併録。感想は書きづらいけど、とにかく面白かったです。2023/09/15
原玉幸子
22
マルクスの功罪である「(産業)資本主義の仕組みの解明」と「理想の実現の為の階級闘争革命」への肉付けの評論を期待したのですが、本書はちょっと違い、マルクスの労働価値説や貨幣に触れていても、寧ろ、哲学の転換点である構造主義への潮流を、ニーチェの哲学、ヘーゲルの論理学、ソシュールの言語学等から眺めた考察でした。私が衝撃を受けた著者『日本近代文学の起源』の端緒となる夏目漱石論『文学について』が並録されていることでも、著者の主意はマルクスマルクスではありませんでした。(◎2021年・秋)2021/10/22