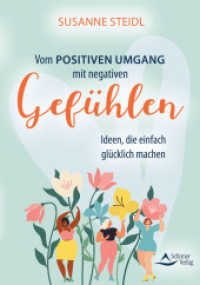内容説明
二六歳の若者がなぜ物理学に革命を起こせたのか?論文から講演録、ラブレターまでを読み解きながら、思索の道筋を平易にたどる。
目次
プロローグ アインシュタイン二六歳、奇跡の年
1章 三大業績への道のり(三大業績とそれ以前の研究との関係;革命的理論へと導いた要因―自伝ノートから ほか)
2章 京都講演「如何にして私は相対性理論を創ったか」(ヴェルトハイマーによるインタビュー;京都講演のテキストと翻訳者 ほか)
3章 相対性理論をめぐる論争(特殊相対性理論はアインシュタインのオリジナルか;武谷三男‐広重徹論争とダリゴルの見解 ほか)
4章 「双子のパラドクス」の真実(宇宙飛行士の寿命は延びるのか;一般相対性理論は不必要か)
エピローグ 波乱の後半生
著者等紹介
安孫子誠也[アビコセイヤ]
1942年、東京生まれ。東京大学理学部物理学科卒。現在、聖隷クリストファー大学教授。理学博士。専攻は物理学史
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゲオルギオ・ハーン
23
2004年発行。アインシュタインの研究の歩み、三大発明の関連性に着目して考え方から相対性理論を解説していった本。物理に詳しくない私としてはこちらの方が分かりやすい。先入観で原点は動かないと思って読んでいては相対性理論の最初から躓いてしまう。考え方の第一歩として計測される方は当然動くが、計測する側、原点もまた動いていると考えなければならなかったとは。いろいろな研究と人との交流をしていたこともあってか視野の広さにも驚いてしまった。2025/04/05
富士さん
1
再読。量子論と特殊相対性理論の説明がとても分かりやすい。著者の教科書書きとしての能力の高さを思わせます。一般相対性理論に関しては把握が難しかったですが、それは微分積分もピンとこない読者の問題でしょう。本書はあくまで科学史の本であって、アインシュタイン自身の説明を利用しながら解説されるので、その辺の入門書を読むなら本書の方がより深く楽しめます。個人的には量子論の基礎になったL.ボルツマンのエネルギーを離散した数とするやり方が、自説を成り立たせるための仮定であったということに科学史のおもしろさを感じます。2016/12/29
ノンミン
0
本書は、アインシュタインがどのように相対性理論を発見したのか論じた本である。 アインシュタインは学生時より、当時の先端であった熱力学などの学問をよく勉強し、先人の正しい業績にものすごく感動・共感する人だったことがわかった。 当時、空間に電磁波を伝搬するエーテルの実体を突き詰めようとする姿が浮かんできました。また、光速を特別な存在と考えていたのだろうと想像した。2015/05/24
norio sasada
0
https://blog.goo.ne.jp/sasada/e/eec267643efd92238bb258a4d63e5c7c https://note.com/norio0923/n/n4a709d3047ac2006/12/03
Steppenwolf
0
G著者は、アインシュタインの著作を読み込んでらしく結構詳しく相対論誕生について議論している。当たり前ではあるが光の量子論ブラウン運動には熱力学の発想が重要であったことを強調されていて相対論でもマイケルソンの実験をアインシュタインの理論誕生に寄与が小さいと主張している。最終章は有名な双子のパラドックス解明に当てられている。ここらの物理を専門とする著者の特徴が現れていて面白かった。2019/07/31
-
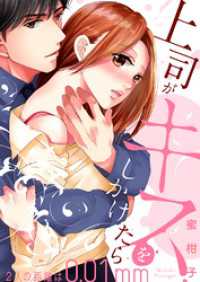
- 電子書籍
- 上司がキスをしかけたら~2人の距離は0…
-
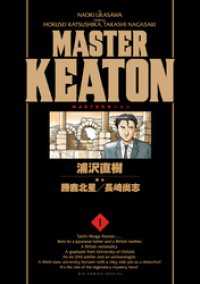
- 電子書籍
- MASTERキートン 完全版 デジタル…