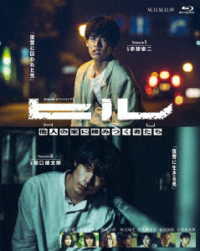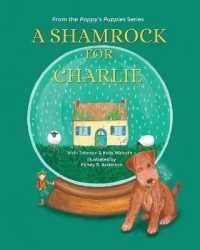内容説明
この世に「在る」ことに何の意味があるのだろう。難解なハイデガーの思索を解きほぐし、存在の深奥を見通す。
目次
第1章 生の実感(存在を問うとはどういうことか;この世の旅人 ほか)
第2章 道―存在解読のメチエ(道としての哲学;変容回路の構造 ほか)
第3章 世界劇場(世界に夢中;ダブルなわたし ほか)
第4章 存在神秘の証明(在りて無き世;底は底なし ほか)
第5章 惑星帝国の歩き方(遠くばかり見ていた;治せない病 ほか)
著者等紹介
古東哲明[コトウテツアキ]
1950年生まれ。京都大学大学院博士課程修了。現在、広島大学総合科学部教授。専攻は、哲学・比較思想
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
文学部生におすすめ本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
43
恐らく読み易いということなのでしょうが、私にとってはほとんど役に立ちませんでした。未読の読者に対しては、ざっくりとしたイメージをつかむのには良いかも知れませんが、私が躓いた問題は、この雄大で大雑把なイメージから、なぜ『存在と時間』で論じられている細かく部分的な論点になるのかということでした。本書は焦点が終始「引き」のようですが、いざテクストを読んだときに上手く入っていくことが出来ない読者を救うことにはならないだろうと予想します。2022/02/22
chanvesa
31
ハイデガーをめぐるエッセイといった位置づけか。ハイデガーのことは知らないので、こういうふうに考えていたという案内はそうなのかと思わせる。163~164頁の「生成と消滅という二つの、たがいに対立し排除しあう動き」という二律背反の上に成り立つ存在というのは細胞とアポトーシス細胞の関係みたいで納得。しかし演劇的な役割に生きることやその虚無感(102頁~)、ニヒリズムをニヒリズムとして生きる姿勢の忘却(220頁~)など、何となく腑に落ちない。ニヒリズム現象と思われるものは散見されるし、忘却されているのだろうか?2017/04/08
テツ
24
先日の旅行からの帰り道でハイデガーの話が出たので読み直し。名著として広く知られる『存在と時間』においてハイデガーが挑んだ「何かが存在するとはどういうことか」という問いについてもう一度考えさせてくれる。ありとあらゆる存在には根拠がなく、存在は常に無(死)と直面している。それをしっかりと見つめ意識する態度の中からは、自らの価値や能力のなさに絶望するような、現代社会に蔓延する精神的な弱さから脱却するための何かが掴めるのではないか。大戦中のスタンスから批判されがちなハイデガーだけれど、若い子たちに読んで欲しい。2022/05/17
またの名
19
もったいぶった専門用語を避けて平易な短文を連ねた文体は、どうして的確で解りやすい至上の入門書。最後の神などのワードも出てきて神秘を強調すると書かれてるキワモノ臭が漂うにしては、『存在と時間』の議論をこんなに見事に身近なものとして理解させる説明力は無二。即座に理解させるのではなく思考を迫るハイデガーの手法を確認しつつもそれに溺れず、世界を劇場と解したりすることで難解な本人の言い回しを読み換える。EreignisやGestellやGelassenheitといった概念もしっかり解説されていて、オススメの一冊目。2016/09/20
パブロ
17
こんな面白いハイデガー解説、初めて! 木田元を始め、いろんなハイデガー本を読んだけど、この本は一線を画している。何が違うのかというと、今ここに「存在する」という奇跡を著者自らの驚きとともに語ってくれていて、その存在の神秘性をぐっと身近に引き寄せてくれるから。ハイデガーの用語の分かりにくさ、というか哲学における特有な文体の難解さの理由もこの本で納得。ふぅ〜、腑に落ちるとはこのこと。キーワードは「至高体験」ってか! とは言いつつも、やっぱりハイデガーは難しい。半分以上も理解できなかったんですけどね、トホホ…。2014/05/09
-
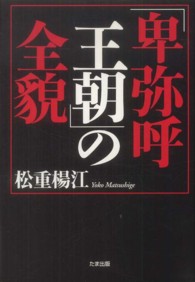
- 和書
- 「卑弥呼王朝」の全貌