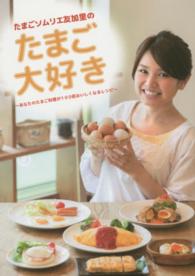内容説明
覚えることは少なくし、仕組みを理解することが算数のコツ。どんな子どもでもかけ算の仕組みがわかると問題を解くのが面白くなる。本当の算数力を引き出す効果のある方法を説く。
目次
第1章 1たす1は本当に2か?(クジラ8頭とサンダル2足は、たすことができるか?;「1+1=2?」は愚問か?;羊飼いの算数 ほか)
第2章 何かおかしいぞ!日本の算数・数学教育(読み、書き、ソロバンは3つのR;動機づけに「ブラックな教材」を;大人の考える系統性は必ずしも正しくない ほか)
第3章 かけ算だけでいいじゃないか!(かけ算は算数・数学の“幹線道路”;いろいろなかけ算;3羽のウサギさんのお耳はいくつ? ほか)
第4章 数学から総合的学習へ(読み、書き、ソロバンの結合;「重さの錯覚」―消えゆくものの共有;無限の世界 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
momogaga
18
数学が少しでもわかればと手に取りました。第3章のかけ算だけでええじゃないか!は目からうろこが取れました。かけ算はまさに算数・数学の幹線道路です。2016/02/12
Kentaro
8
1足す1は本当に2でいいのかといった投げ掛けから始まり、二次関数や微分や積分、といった考え方がどうなりたつのか等を理解できる。クジラ8頭とサンダル2足は数えられるか、10だと答えた子供に単位が異なるものは数えられないことを教える事から始めてみよう。時速75kmで壁にぶつかったら何メートル上空から落下したのと同じなのか、そんな事も平易に理解したつもりになれます。数学から物理学に踏み込むと更に興味が湧いてくる事象が増える。「要約力、コメント力」つまり日本語を自在に操る国語力と算数、物理から来る論理力が必要だ。2018/11/16
みさみさ
2
どうしてこうなるの?そう決まってるんだよ。なんで?……ルールはわかる。計算もできる。でも、数学的に考えたり、数学を活用することはできない。数学のできない大学生が嘆かれるなかで、小さい頃のなんでなんでにぜひ着目したい。色々な角度から考えさせて自分で発見させる。なんでなんでにとことん付き合う小学校算数の授業や、家庭教育ができるといいね。2014/11/09
三木
2
紹介されるような無邪気で自由な発想で数字と向き合えたらどれだけ楽しかっただろうと思う。「本来はこういう風に考えるものだ」って改めて説明されてもすぐはピンと来ないし、根付いた「やり方」だけの数学はなかなか元には戻らないですね。2011/01/08
ジャーマン♪
1
ブラックな授業による「対話の動機づけ」という視点を大事にしたい。2013/08/20