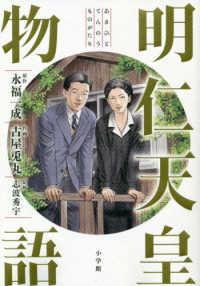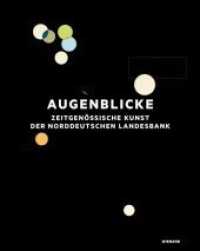内容説明
「神々の島」「芸術の島」は、いかにして生まれたのか。バリ、パリ、ニューヨークを結んで織りなされた植民地時代の物語をたどり、その魅力の深層に迫る。
目次
第1章 植民地としてのバリ―バリ文化とオランダの統治(一枚の記念写真;王国と戦乱;帝国主義と倫理政策 ほか)
第2章 パリにきたバリ―一九三一年国際植民地博覧会とオランダ館(オランダ館とバリ;ヒンドゥー的な色彩;バリがパリにくるまで ほか)
第3章 ニューヨークのなかのバリ―ミゲル・コバルビアスと『バリ島』(ベストセラー『バリ島』;マンハッタンの寵児;バリ島への新婚旅行 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
noko
2
大好きな場所バリ。何度も旅人として行ったけど、バリ島の美しい部分だけをみて(嫌な部分にはあえて目を向けないようにして)きた気がする。でも、現地の人と偶然知り合いになり話を聞き、バリの真の姿を知れた。この本を読んで益々、納得。バリ島には階級があり、植民地時代から人が人を監視していて、身分が低い人は、苦労する。また、宗教はバリヒンズーが圧倒的多数を占めているけれど、イスラムの人も少数だけどいて、イスラム教徒に対するイジメは凄いそうです。2013/02/01
サアベドラ
1
オランダに植民地化されるバリ、パリの植民地博覧会に出展したバリ、コバルビアスによって描かれニューヨークで出版されたバリと3つの時間地形軸によってバリを描き出す本。重要なのは征服時にオランダ植民地政府によって確定されたバリに対する文化的価値観である。ある意味、現在のバリの文化的風景はこのとき作り出されたとも言える。すなわち「見せる」文化としてのバリ文化である。コバルビアスはバリ文化を描くことでこれを打ち破ろうとしたがやはりそこから抜け出せることはできなかったという。オリエンタリズム?2006/05/27
★★★★★
0
過大評価気味のワルター・シュピースは敢えて排除して、バリの観光開発史を人類学的側面から記述した本。面白い。2008/03/16
キノコン
0
国際植民地博覧会とミゲル・コバルビアスから見たバリ島について、知らなかったことばかりです。シンガラジャがとても大事な港だったことも初めて知って、私の中の小さな世界地図が少しずつ繋がっていきました。バリニーズ、なかなか強かです。生存戦略としての伝統芸術かあ。でも素晴らしいんですよね〜。コバルビアスの「バリ島」も読んでみます。2025/04/02
kure
0
あたかも自明のもののように考えられていたようなバリの「伝統」的な「文化」というものが、いかに植民地的現実のなかで語られてきたのかが論じており非常に興味深い。名著として再版されるべきだと感じた。2021/05/29
-
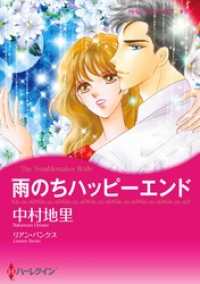
- 電子書籍
- 雨のちハッピーエンド本編