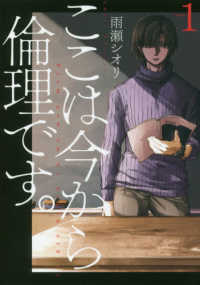内容説明
陽気かつ沈鬱、奔放かつ禁欲的なロシア人が、社会主義革命の後に得た強制の装置ソビエト。広大で苛酷な自然に育まれたロシア人は極端な二面性向のゆえに長い停滞と激烈な変革の歴史を築いてきた。チャーチルをして「謎の謎」と言わしめて民族の心性をさぐる。
目次
ムジークとプロレタリア―ロシア的気質と行動原理
血塗られた権力―国家支配の歴史と原理
戦争と膨張―ロシアはいかにして超大国になったのか
よみがえる神々―ロシア正教と共産主義
ロシアは東か西か―インテリゲンツィアの系譜
裏切られた革命―なぜスターリン独裁が生まれたのか
ソ連がロシアでなくなる日―ペレストロイカの実験
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
yes5&3
3
再読。ゴルバチョフがペレストロイカを進めていた頃の本。神聖ローマ帝国に関する本を読んだ後、同じ時期のロシアがどうなっていたかと30年ぶり('91/2/17以来)に再読。記憶に残っていたのは、ツァーリの神格化「悪いのは皇帝でなくそれを支援できない周囲だ」、民族主義(スラブ主義)と西欧化(キャッチアップ)の繰り返し、の二つ。独裁者の系譜、イワン雷帝が日本の戦国時代にロシア統一、ピョートル大帝が明治維新の頃、西欧化、日露戦争、ロシア革命、第一次世界大戦後のスターリン、ロシア正教の影響。ときどき読み返すべし。2019/11/08
荒野の狼
3
1991年のソ連崩壊前の1989年12月発売の書。本書の魅力は、旧ソ連の人々の民族性が歴史とからめてコンパクトに書かれている点。ソビエト及びロシアの歴史の細かいところは他書にゆずるとして、本書の執筆時点では、筆者はゴルバチョフに共感するもののペレストロイカがうまくいっていない状況は割に詳しく書かれている2019/07/04
じむくろうち
3
ウクライナが国際情勢の表舞台に上がって来たので積読していた本をひもといた。ロシアの現在のウクライナや欧米諸国に対する対応は、昔から少しも変わってないことが分かる。ロシアを理解するには、歴史を知ることだと思った。ペレストロイカが始まったばかりでベルリンの壁崩壊前に書かれた本。筆者の未来予測は当たっているようで当たっていないところもあり、今読むとおもしろい。2014/05/13
Yam
2
ソビエト崩壊前のロシアを、崩壊前の視点から語られており興味深かった。2017/07/22
Jun
2
ロシア、ソビエトについて余りにも無知だったので、とりあえず読んでみた。ロシアの大まかな歴史や、民族性、またソ連解体という事件がいかに難しく大きな物であったかがわかった。生まれたころから「ロシア」の世代で、このあたりの出来事に余りにも疎く、理解しきれない部分もあった。また別の本も読んでみたい。今度は解体後の本がいいかな。2013/06/24
-

- 洋書
- GRABIDE