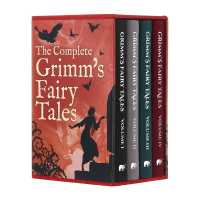出版社内容情報
【内容紹介】
須弥山とは高さ56万キロ、33人の天神が住む想像上の高峰である。紀元5世紀、インドで集大成された『倶舎論』は、この須弥山にはじまり、人間が宇宙をどう把えていたかを、詳細に描写している。本書は、この『倶舎論』を基礎に、仏教の宇宙観の変遷をさぐり、輪廻と解脱の2つの思想の誕生・発展の経緯を明らかにし、その現代的意味を説く。
輪廻と解脱の思想――仏教にはさまざまな経典や言葉があるけれど、結局は輪廻と解脱の2つの思想に帰するといえよう。仏教者はこうした輪廻的宇宙と解脱への道との両方を、それぞれ吟味し、研究し、やがてそれらを1つの壮大な体系にしたてあげた。そのような体系を示す書物の1つに、インド5世紀の仏僧ヴァスバンドゥの『倶舎論』がある。この中に須弥山説と呼ばれる仏教宇宙観が示されている。これが、後に“地獄と極楽”にまつわるさまざまな考え、描写へと発展し、日本にも大きな影響をあたえた。一見、過去のもの、われわれとは無縁のものと思われる仏教宇宙観も、実は、いまや新しい世界観を樹立する上で、重要な役割をになおうとしている。――本書より
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
マーブル
8
「仏教の世界観は破産している」 最後の章で作者は述べている。 それは人生=苦として、そこからの解脱を目的としていた仏教が、次第に人生=楽、人生(現世)での成功や幸福を求める風潮の中で変化しながら形骸化し、ついには実生活とは無縁の「神話化」してしまった、と主張する。 ここまで、多少混迷、多岐に紹介されてきた仏教宇宙の話題は、実はその変化の段階ごとに書かれていた事が分かる。時代に合わせ、国に合わせ、変化してきた仏教。それは一仏教に限ることではあるまい。 2018/02/16
in medio tutissimus ibis.
2
仏教の、というか『倶舎論』に展開される宇宙観。説一切有部は仏教の中でも異端ながら体系的なために重視されてもいたという微妙な立ち位置で、仏教の、とするのはどうかなとも思ったり思わなかったり。ここで展開されるのも、覚りを得るための知識としての世界論なのであって、あからさまに図式的。曼荼羅に近い。天界や地獄などの上下方向への考察に比べ、水平方向への考察が乏しいのもその表れか。西方浄土という水平方向のアイディアは、覚り(上昇)よりも菩薩行を重視した大乗仏教らしい発想だと思う。あるいは仏教の西進とも関係するのかも。2017/04/20
しゅう
2
☆☆☆ 極楽や地獄がお釈迦様の法論でなく、後の大乗仏教の興隆期に考えられたものだということ、エジプト・ギリシャ・ローマ、ユダヤ、キリスト教、ゾロアスター教などの宗教的世界観が影響しあっていること、ギリシャ宗教がいつしか神話という物語になるように、宗教は長い年月ののち形骸化して物語になっていくことを知った。2013/05/19
竜王五代の人
1
須弥山や、人類の世界である金輪上の地形など、仏教の(インド的な)世界観が図解で示され分かりづらくはないが、羅列されてもとにかく桁の大きさに圧倒されるばかりである。須弥山の高さ8万由旬(56万キロメートル)なぞエベレスト(高さ9キロメートル弱)どころか地球直径1.27万キロも比べ物にならず、月までの距離(38.5万キロ)で対比できるぐらいである。しかもこれも序の口。まともに受け取るよりは概念的なものと考えるべきだろう。/時間や物質観にも触れている。2021/01/15
higurasias
1
最初に読んだのは、光瀬龍の「百億の昼と千億の夜」読了後。もう30年以上前。あの精緻な宇宙観に惹かれて。
-
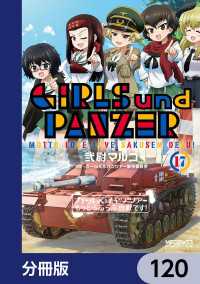
- 電子書籍
- ガールズ&パンツァー もっとらぶらぶ作…