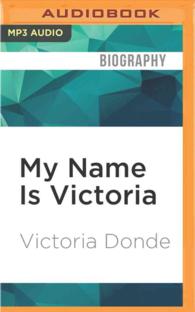出版社内容情報
【内容紹介】
本はどう読み、どう役立てたらいいのか。効果的な読み方はないものだろうか。本書は、本の選び方、読み方から、メモのとり方、整理の仕方、外国書の読み方まで、著者が豊富な読書経験からあみだした、本とつきあう上で欠かすことのできない知恵や工夫の数々をあまさず明かし、あわせて、マス・メディア時代における読書の意義を考察した読んで楽しい知的実用の書である。そして同時に、ここには、読書というフィルターを通して写し出された1つの卓越した精神の歴史がある。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
momogaga
30
読メ開始以前の既読本。1972年に知の巨人の読書論として、ありがたく読みました。
kubottar
25
洋書の読み方が特に参考になった。読書法の本はたくさん読んだが、やはり古い本にこそいいことが書いてあるかもしれない。2016/10/16
TS10
24
社会学者である著者の体験をもとに語った読書論。教養書を特徴づけるものは、それが著者にとり秩序だった抽象的な諸観念から構成されるということであり、従って、読む者には無秩序にも感じられ緊張が伴う。しかし、その後読んだ内容について読者自身が表現することにより、読者に秩序だった形で観念を整理し直すことができる。こうした主張が全体から読み取れる。また、感覚器官をより効率的に動員するテレビと比べ書物が優れているのは、観念の伝達においてであり、そこに精神生活を向上させる理由がある。2024/03/20
501
24
長年培った経験をもとに紡ぐ言葉は深い。本との関係が豊かになる向き合い方を簡にして要を得た文章で語る。背筋を正したくなるぴりっとした機知で諭し、知らず知らずのうちに凝り固まってしまう本の読み方をほぐしてくれる。2015/05/12
白義
23
どう読むか、といっても具体的技巧に凝ったものではなく、いわば清水幾太郎という昭和時代の大知識人がいかに本を読んできたか、読書という行為をどう捉えているかという自伝的な読書論。江戸っ子気質で知られる著者だけあり本は蕎麦のようなものだ、一気に読み切れ、古典だとか世間の流行とかも気にするなとざっくばらんで徹底的な自分中心の主観的、プラグマティックな読書観が特色。いかに買い、売り、捨てるかというところまでテクニックではなく体験として書かれているので読み物としての連続性が高く実用性と娯楽性のバランスが高い一冊である2016/08/12