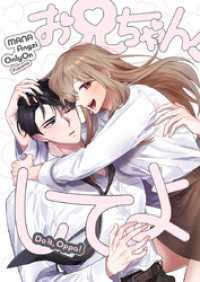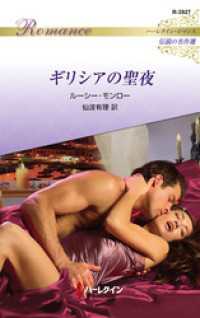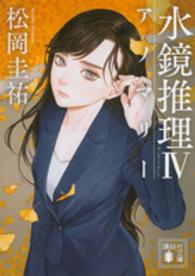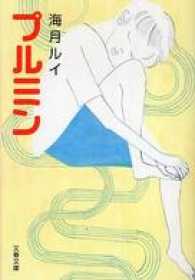出版社内容情報
【内容紹介】
人間は「考える」ことなしには生きてゆけない。よりよく生きるとはよりよく考えることである。よりよく考えるにはどうしたらいいか。論理的に誤りのない「正しい」判断ができるだけの心構えと論理を身につけることである。本書は、ともすれば陥りやすい論理や判断の落し穴を具体例に即して教えた、考えるための手引書である。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Defricheur
11
哲学者である筆者が「真に論理的に思惟するということは決して非現実的な観念的な思惟を行うということではありません」と語ることには、非常な重みが感じられる。徹底して思考するとは、常に具体的な例を想定して考え抜くことであり、抽象的な命題・論法に逃げないということである、という厳然たる事実を、極めて平易な筆致により示す。2021/07/28
哲学する読書家@埼玉|対話と発見の案内人
6
哲学のすすめに続く本作、これも面白かったと記憶してる、読んだのは高校生のとき、20年以上前である。一番心に残ったのは左と右とか、極論を排して中間をとる方法もあるよと書いてあったこと。当時はマスコミの左派的姿勢と、一方で小林よしのり氏を中心とした右派、保守派が形成されつつあり、ためになった。大学に入って過激派が学内を占拠していて、生涯右派とか左派とか、イデオロギーが関わったと思う。今の日本もSNSでイデオロギーは最重要なこととなってる感じがする。
ねこなのか?
5
古い本だけど、今こそ価値がある本だと思う。 最近は「いいね」の数が正しさの指標になったり、誰かの言うことを極端に信じたり、逆にすべて誤りだと考えたりと、正しく考えられていない人がSNS等に溢れている。 だからこそ、こういう類の本は1冊は読んでおいて、何か考える時に、陥りがちな判断(考え方)の間違いをしていないか立ち返ってみるのが良いと思った。 また、マルクス主義や快楽主義への批判もあって時代を感じてそこも良かった。 否定のための否定ではなく、肯定のための否定である批判的精神を常に持っておきたい2022/07/27
やっさん
3
批判的精神という題で小学校か中学校の国語の教科書にあり、自分のその後の考え方に多大な影響を与えた文章をもう一度読みたくなり購入。権威、過信、常識にとらわれることなく、正しく考えることが大切だと述べています。現在はインターネットが普及し、この本が書かれた頃よりも入ってくる情報量が格段に多く、正しい情報を元に正しく考えることが更に難しくなっているように思います。間違った事実判断を元にして、誤った価値判断がなされる。現代の混乱はそんなところに問題の根元があるように感じました。自分自身も思いを新たにする一冊でした2013/03/26
ミラノ
2
正直、後半からよく分からなかった。まるで数学の証明みたいでした。前半はけっこうへーとなってためになりました。2025/12/17