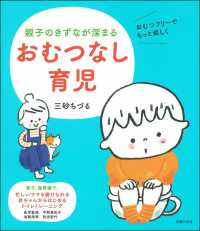出版社内容情報
【内容紹介】
言葉と文化、言葉と思想・感情は、密接不離な関係にある。なまじ・いっそ・どうせ・せめて・さすが・しみじみ……。私たちが日頃無意識に使っているこれらの言葉は、いかなる文化伝統に生まれ、私たちをどのように性格づけてきたか。長年アメリカにあって外国人に日本語や日本文学を教えてきた著者が、こんな翻訳不可能ともみえる言葉の底に、日本人独特の論理や価値観をさぐりだしたユニークな日本文化論。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
著者の生き様を学ぶ庵さん
36
どうせ、せめて、さすが、しみじみ。こういった英訳しにくい日本語らしさに注目した日本人論も高校生の頃、現代文の久保寺亨先生に紹介されて読んだ訳ですよ。現代文の低過ぎる点数をどうにかしたいという極めて不純な動機から読書の世界に入門したのですね。2016/09/27
壱萬参仟縁
28
初版1971年を読んだ。図書館除籍本。責任回避の心理:いずれしかるべき者から御返事申させることにいたしまして、大体においてこうじゃあないかと感じましたことを申し上げますというところで今日のところは御許し願いたい。→きわめて良心的な厳密かつ丁寧な言い方のように見えて、相手を煙にまき自分の尻尾をつかまれないための巧妙な まじない(傍点)言葉であり、ずるがしこい責任のがれ(16頁)。2021/01/22
tolucky1962
8
じゃないが:責任回避の予防線。みんな:無意識な二値的思考。いっそ:迷った末の次元を超えて意思決定。どうせ:突如議論を中絶。なまじ:完璧主義ゆえの妥協で大衆の心をくすぐる負の感覚。せめて:不満を忘れるささやかな満足。わび:せめてを磨き上げ高価値に転化。られる:判断の主観を避ける。なる:決定を自然発生とする責任回避。なのですが:自発的答えを待つ要求。やはり:根拠は示さない選択。2024/07/06
まさや
7
「なまじ」「やっぱり」「どうせ」などの言葉がどのような構造で使われているかをアメリカで日本語を教えていた著者が書いています。なまじ、無意識に使っているので、意識にあがると、やっぱり、奇妙な気分になります。 2021/04/27
ハパナ
7
1971年に出版で、半世紀程前に書かれた本です。日本文化における論理構造と、その言語論とでも言い換えられるのではないか。定規でピシパシと線を引いて行く西洋的な見方とは違うが、日本にも合理的な筋道を立てる考え方がある。言語という道具は文化や習慣から生まれるが、何かを表現する時には逆にその言語の範囲内という制約を受ける。なので、日本語に特有の語句から遡ってその文化の論理構造を読み解くという内容です。しかし、真面目な本文の中に突然”アクメ”や”白痴”等の語句が出て来て、驚くと共に時代性を感じました。2016/09/16