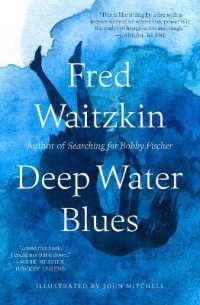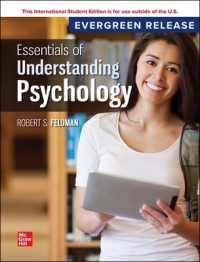出版社内容情報
戦国のみならず江戸以降にも「バサラ者」は現れた。奇矯な振舞いで知られる戦国~幕末の11人を紹介、その系譜を明らかにする。
奇矯な振舞いで世を驚かす戦国武将は「バサラ者」と称されたが、その系譜は江戸以降にも引き継がれ、常識にとらわれない異能の人物により歴史は突き動かされてきた。戦国~幕末までのバサラの名にふさわしい11人を取り上げ、その闇のパワーを明らかにする。
【著者紹介】
1922年福島県生まれ。東洋大学文学部卒業。雑誌編集者を経て作家活動に入る。歴史小説を中心に執筆を続け、『斗南藩子弟記』、『紅葉山』がそれぞれ直木賞候補となる。近著に『戦国梟雄伝』(学研M文庫)など。
内容説明
奇矯な振る舞いで世を驚かす武将を「バサラ者」と称する。その系譜は鎌倉末期、南北朝に始まり、戦国、江戸、幕末と引き継がれ、常識にとらわれない異能の人物により歴史は突き動かされてきた。戦国~幕末までのバサラの名にふさわしい11人を取り上げ、時代を闊歩したそのパワーを明らかにする。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ちばっち
4
11人も取り上げられているので一人ひとりが短くてアッサリした感じに仕上がっていたので残念でした。もう少しじっくり読みたかったです。私のNo.1は佐々木道誉です。バサラや傾奇者を語る上で一番必要なのは「風流」や「粋」だと思います。これが無いとただの変わり者になってしまいます。この二つを見事に感じさせてくれたのが佐々木道誉でした。格好良い!No.2が池田治政でNo.3が岡左内かなぁ。2016/01/17
なつきネコ@着物ネコ
1
バサラと言うよりは、時代の中で鮮やかな生き方した人々といった感じ。 江戸期のバサラ者の生き方はグレたツッパリを思い浮かぶが大久保彦左衛門の意地を張る生き方は、当時からしても憧れなんだろうな。私としては鮮やかでないけど時代を関係なく生きた平山行蔵に憧れるな。話としては切り口が変わっていた池田治政や、岡左内かな。しかし、ツッコミ所もあった。景勝様が笑いすぎて、腐女子歓喜の慶次×景勝かってぐらいに。後は著者は甲冑に詳しくないな。慶次の旗指物と陳羽織は一緒に使えないし、左内の角栄螺の兜はこの時代はない。2013/10/06
takao
0
ふむ2017/10/30
akamurasaki
0
室町創立期から幕末まで、バサラな生き方で時代を駆け抜けた11人の武人の短編集。どうしても戦国時代の人材が厚いため、関ケ原や大坂の陣のエピソードがかぶりまくっていましたが、バサラ大名の元祖佐々木道誉から幕末の武士の終焉に立ち会ったといえる将軍家御庭番の小芝長之助まで、様々なバサラの形をまとめてみることができました。2016/12/27
Stella
0
バサラ者紹介というより短編小説風。サブタイトルに「戦国〜幕末」とあるわりには、きちんと佐々木道誉が取り上げられていた。2012/09/24
-

- DVD
- 銀魂 後祭り2023(仮)
-

- 電子書籍
- 事業をスケールさせる4つの方策 DIA…