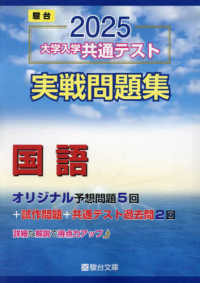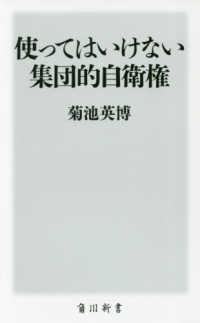内容説明
戦国時代の武将や兵たちは、何を食して活力となし、戦い続けることができたのか。体力と気力の限りを尽くす戦場において、食は勝敗生死を分ける重要な課題である。食文化史・食復元研究の第一人者である著者が、栄養や携帯性を考えた戦闘食、兵站を支える技術、活力を養う日常食などを紹介する。足軽の携帯食や武将の日常食、豊臣秀吉の豪華膳も再現。
目次
第1章 武将たちの食の知恵(戦国一の人気者、秀吉の天下取り食;秀吉の天才的な兵糧策 ほか)
第2章 戦国を生き抜く勝負食(湯漬け、焼き味噌は先手必勝の勝負食なり;最期に賭けた「にら雑炊」 ほか)
第3章 戦場で勝つための食べ方(いざ出陣と腰兵糧;勝つための出陣の儀式)
第4章 「籠城食」で生き残れ(命をかけた戦国の知恵)
第5章 武士めしの“最終兵器”(兵糧丸;水渇丸と酒)
著者等紹介
永山久夫[ナガヤマヒサオ]
1932年福島県生まれ。食文化史研究家。西武文理大学客員教授、綜合長寿食研究所所長。日本の伝統的な食文化の研究を続け、和食による健康・長寿を提言。NHK大河ドラマでも食膳を再現するなど食文化史・長寿食の第一人者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
猫
9
図書館本。戦国時代の武士が何を食べていたかが検証されている。せっぱつまっていない時の食として紹介されている物は普通に美味しそう。有事の食とその備えは理にかなっている上に凄味があって、経験のすごさを感じる。塩さえあれば毒のない大抵ものは食べられちゃうんだなぁ…。食の効能と武将の性格や寿命の結びつけはやや強引。あと、この著者が秀吉を好きだというのはわかった。2015/11/08
金目
8
武将が食べていた物とそれに含まれる栄養素についての解説が面白い。味噌の効能とか見ると、旨い物が食べられる地域の人間が意識的に健康食を取っていたから天下が取れた、という印象を受ける。戦国時代は慢性的な飢饉状態だったと聞いているけれど、救荒食や籠城食の話を見ると、こんな物まで食べていたのかと驚かされる。松って非常食なんですねぇ。健康オタクの家康も75歳で死んでるのに、八丈島に流された宇喜多秀家が、魚介と菜っ葉で84まで生きたというのはびっくり2019/12/11
hitbari
3
食術より、エピソードが、面白かったが、後半くどかったかな。2018/05/04
M_Study
3
戦では、三日分の食料は自前で腰に兵糧を巻きつけるなどして戦っていたとは驚き。また、食料不足に備えて、戦国武将の普段の食事は非常に質素だったというのも初めて知った。口絵には饗応食のカラー写真があるが、現代から比べるとだいぶん質素。テレビドラマとかでは目にすることがない、リアルな戦国時代が感じられる一冊。2016/03/24
S_Tomo🇺🇦🇯🇵
3
腹が減っては戦は出来ぬ、というくらいなので戦国武将も人の子、お腹が空けばご飯を食べます。 そんな戦国時代にどんなものを食べていたかを記した本。 出てくる食事は普通に美味しそうですよ。2012/11/11
-

- 和書
- 魂のおいしいたべもの