内容説明
本願寺は親鸞を開祖とし、その法脈と血脈を伝える者が宗主として継職した。その教えは八代目・蓮如の布教により、戦乱の世に怯える民衆の間に燎原の火のように広まった。そして戦国時代、天下統一の野望に燃える織田信長の前に立ち塞がり、豊臣秀吉との葛藤、徳川家康による封じ込めなど、三人の天下人との長い戦いが繰り広げられることになる―。仏教団の雄VS戦国の覇者、天下人と民衆教団の長く激しい闘争の全貌に迫る。
目次
第1章 織田信長と本願寺の戦い(信長が本願寺に要求したものとは;本願寺と信長の十年合戦の開始 ほか)
第2章 本願寺の退去と信長の死(本願寺に協力した毛利氏の思惑;本願寺との和睦を朝廷に頼った信長 ほか)
第3章 豊臣秀吉と本願寺の戦い(天皇の命で和解した本願寺の父子;賎ヶ岳の合戦に協力した門徒勢力 ほか)
第4章 秀吉に翻弄される本願寺(防衛都市の京都に置かれた本願寺;本願寺宗主を交代させた秀吉の意図 ほか)
第5章 徳川家康と本願寺の戦い(三河の一向一揆を弾圧した家康;本願寺に協力を求めた家康の変心 ほか)
著者等紹介
武田鏡村[タケダキョウソン]
1947年、新潟県生まれ。日本歴史宗教研究所所長、作家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
田中峰和
4
半世紀のうち、10年は信長との合戦であった。大坂石山の地を追われ紀州鷺宮に退去した顕如は、その後も秀吉によって和泉の貝塚、大坂の天満、京都へと移転を繰り返した。当初は堺の会合衆が矢銭を拒否したのに対し、本願寺は素直に納入したがその後も続く無理難題に、ついに抵抗を始めた。本願寺と天下人との関係は、信長が餅をつき、それを秀吉がこね、家康が食べたという譬え。現実には信長が本願寺と戦い、秀吉が懐柔し、最後に家康が完全に統制下においたという50年の歴史が記録に残る。2021/05/18
スプリント
4
信長・秀吉・家康の本願寺への対応はまさに「ホトトギス」の例えどおりだと感じました。信長の時代にあれだけ猛威を振るっていた僧兵勢力を解体した秀吉の手腕はさすがですね。2014/06/27
めぐみこ
2
信長が本願寺と戦い、秀吉が懐柔し、家康が完全なる統制下におく。そんな天下人vs本願寺の戦国史ダイジェスト。本願寺の裕福さ、権力の強さがここまでとは。堺にも劣らぬ財力と海外交易を行う力と土地の利を持っていたなら、天下人たちが無視できないのも道理だ。信長とガチンコ勝負できたのは結束の強さだけではなかったと判った。元々親子げんかだったのが、豊臣方に味方する西本願寺vs徳川の保護を受ける東本願寺という構図に至るあたり、宗教戦争は怖ろしいものがある。2018/07/13
maito/まいと
2
知る人は知っている。信長の天下布武最大の障害は、信玄でも謙信でも毛利でもなかったことを・・・中世から近世への転換期の中で生まれた、権力と宗教との激突を描いた一冊。信長を最も長く苦しめた石山本願寺、その背景と経緯、そして秀吉・家康と権力者が移る中で、本願寺はどのように変わり、どのように近世を迎えたのかが解説されている。特に家康時、本願寺内のことが、権力者にお伺いを立てなければ決められなくなったという展開は、権力と宗教が結びついてしまったという、時代の移り変わりを感じさせる。2012/04/27
孤独な読書人
2
秀吉と家康が本願寺に対してどのような対策を打ったかが分かる。2012/03/08
-
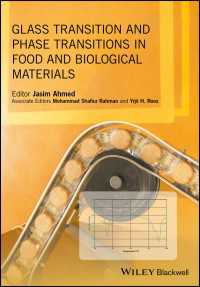
- 洋書電子書籍
- Glass Transition an…
-

- 和書
- 本から生まれるものは愛






