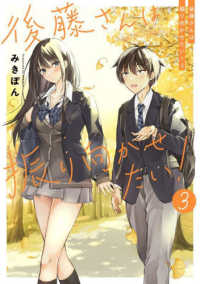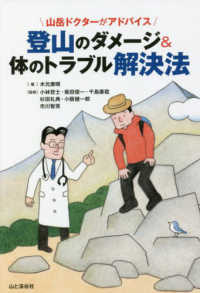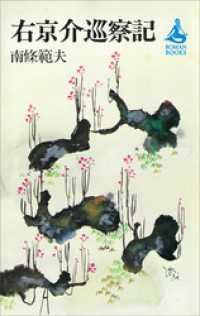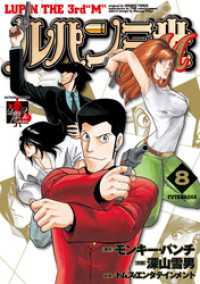- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 特別支援教育
- > 知的障害・発達障害等
出版社内容情報
通常の小中学校の児童生徒の6㌫がLD・ADHD・高機能自閉症であるという。しかし専門性のない通常学級の教師は子ども達の困り感に合った支援、教育ができない。そこでその具体的な支援策を実際の事例から教える本である。
内容説明
本書は、通常の学級に学ぶLD・ADHD・アスペルガー症候群などの発達障害のある子どもたちが、学校での生活や学習のどういう点につまずき、「困り感」を抱いているか、その背景を解明して、それぞれの子どもに合った具体的な支援の手立てを紹介した特別支援教育、指南の書。
目次
発達障害のある子どもの「困り感」とその背景に気づく
支援の手立て(教室でできる支援の手立て;教室内のトラブルへの対応;学びを支える個別支援;生活を支える個別支援;崩れた学級を立て直す)
保護者とともに子どもを育てる
周りの子どもとその保護者への対応
組織的支援の手続き
著者等紹介
佐藤暁[サトウサトル]
1959年、埼玉県生まれ。筑波大学第二学群人間学類卒業。同大学院教育研究家修了。岡山大学助教授(教育学部障害児教育講座)。博士(学校教育学)。専門は、特別支援教育臨床。数多くの学校・幼稚園・保育園を訪ね、現場の実情に合った特別支援教育のありかあを模索している
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
碧子
1
目で見てわかるような工夫。タイムテーブルの作成張り出し、イラストや写真の活用。次になにをすればいいか、今はなにをするための時間か、それが分かれば確かに安心する。その場にそぐわないような行動もみんな意味はある。その子なりの意味はある。そこを汲み取ってからその次へ進む、なるほど。祥一君のご家族のご理解と協力体制には頭が下がる。その中での「もう、十分頑張ったじゃないか」というお父さんの言葉の重さ。我が子と寄り添い歩んできた親でこその言葉。2014/09/21
そむたむ
0
特別支援といえども、自主性に溢れている子ども集団を作ればそれが最大の支援となることを改めて感じた。 2014/08/09
epitaph3
0
10年前の本になるも、方向性は今も通用する。再読し、自己の実践を振り返った。2008/06/14