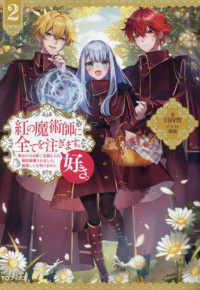内容説明
あなたがオーケストラの壮大な演奏に感動し涙を流すとき、ジャズライブでのパフォーマンスに興奮して身を乗り出すとき、脳内ではこんなことが起こっているのです―。音とリズム。ただそれだけの要素で組み合わされたノイズが、耳から入ってどのように処理され、劇的に音楽に変わり、そして人の心を動かすのか。自らも音楽家である認知科学者が素朴な疑問に端を発し、ブードゥー教の音楽からベートーベンやガーシュウィン、ボブ・ディランに至るまで、様々な実例を歴史と科学、両方の見地から分析。音楽成立の壮大な謎に迫る。
目次
音楽にまつわるいくつかの話
第1部 集合力学(音楽と結びつき;ホタル―力学と脳の状態;音楽的意識と喜び)
第2部 音楽と心(夜のブルース;リズムメソッド;きらめく瞬間)
第3部 音楽文化の進化(原人たちのリズムバンド;世界を歌う;音楽と文明;ジャズ時代と未来)
著者等紹介
ベンゾン,ウィリアム[ベンゾン,ウィリアム][Benzon,William L.]
認知科学者。雑誌“Journal of Social and Evolutionary Systems”を共同編集するかたわら、音楽活動にも積極的にかかわる。ミュージカル・アンサンブルAfroEurasian Connectionの創設者の一人。ニュージャージー在住
西田美緒子[ニシダミオコ]
翻訳家。津田塾大学英文学科卒業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きゃれら
19
音楽するというのは、演奏だけでなく聞く、踊るという音楽をめぐる営み全部を示していて、その時脳の中で何が起きているのかについて、幅広い著作から引用しながら著者の考えを書いたエッセイだ。読み続けるのに苦労したけれど読んだ甲斐はあって、今後の音楽鑑賞に変化が起こりそう。原著は20年以上に前に書かれていて、2005年12月刊行の直後に入手したまま積読だった。読メでも密林でも厳しい批評しか載ってないし、その批判は結構正しい。最新知識に基づく書き直したバージョンを再読したいのが本音。結構面白いこと言ってると思う。2023/06/29
すずか
1
音楽の効果とか人間との歴史を脳科学的な視点で説明してる あーはい、音楽ってすごいですねーって感じ2023/11/05
ふみ
1
第一部:音楽とは、共同の営みを通して個人の脳をお互いに結び付ける媒体である。 第二部:脳の内部で、音楽が感情→リズム・構造→喜びと恍惚に変わっていく様子に注目する。 第三部:猿→原人→20世紀までの音楽文化の流れ 人間の脳は音楽をどう生み出したか主に認知科学の観点から論じた本。著者は認知科学者兼ミュージシャンであり、自らの音楽体験も織り込みながら、音楽が人の脳に相互的に作用を与え社会の形成を媒体していく様を描く。対象の音楽は西洋~20世紀米国に偏っているが現代人の志向を説明するにはさしあたって十分?2013/01/23
かわかみ
0
著者はデカルト的な「我思う」方法論は採らないと述べている。音楽は複数の人間の間で交感するものだからもっともだ。しかし、デカルトの情念論に似た脳科学的な方法論で何が明らかになったのか。認知科学で音楽を整理しなおしただけであり門外漢にはラベルの貼替えにしか見えない。たとえば、なぜ人は悲しい音楽を好んで聴き、しかも苦痛ではなく快く感じるのかと問題提起しているが、結局「謎だ」で終わっておりがっかりだ。さらに社会における音楽の機能、歴史になると社会学・人類学を援用した寄木細工の屁理屈である。総じて著者の自己満足だ。2021/07/25
MASA123
0
図書館で借りるのは二度目ですが、今回も、4分の1も読むことができなかった難しい本です。引用が多すぎて、論旨に集中できないというのもあります。訳者あとがきによると、認知科学という難しそうな分野の研究を音楽に適用したもののようです。 音楽を聴いたり演奏したりするとなぜ、楽しいかが、わかるかと思ったけど、読解力がないと読めない本でした。ああ、しんど。 2021/04/07
-

- 洋書
- DESORDRE