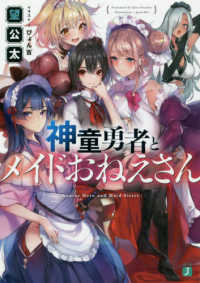- ホーム
- > 和書
- > 新書・選書
- > 教養
- > 角川oneテーマ21
内容説明
ベストセラー『日本人とユダヤ人』で有名な評論家・山本七平は戦時中フィリピンで生死を彷徨い捕虜となった。戦後三十年、かつての敗因と同じ行動パターンが社会の隅々まで覆っていることを危惧した山本七平が、戦争体験を踏まえ冷徹な眼差しで書き綴った日本人への処方箋が本書である。現在、長期の不況に喘ぐ中、イラクへ自衛隊を派遣し、国際的緊張の中に放り込まれた日本は生き残れるのだろうか…?執筆三十年後にして初めて書籍化される、日本人論の決定版。
目次
目撃者の記録
バシー海峡
実数と員数
暴力と秩序
自己の絶対化と反日感情
厭戦と対立
「芸」の絶対化と量
反省
生物としての人間
思想的不徹底〔ほか〕
著者等紹介
山本七平[ヤマモトシチヘイ]
評論家。ベストセラー『日本人とユダヤ人』を始め、「日本人論」に関して大きな影響を読書界に与えている。1921年生まれ。1942年青山学院高商部卒。砲兵少尉としてマニラで戦い補虜となる。戦後、山本書店を設立し、聖書、ユダヤ系の翻訳出版に携わる。1970年『日本人とユダヤ人』が300万部のベストセラーに。日本文化と社会を批判的に分析していく独自の論考は「山本学」と称され、日本文化論の基本文献としていまなお広く読まれている。1991年没(69歳)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あちゃくん
39
この本に書かれている小松さんや山本さんが指摘した敗因を現代日本が克服できているかを考えると、その心許なさに落胆する。2022/09/05
ちくわん
24
2004年3月の本。いや~ぁ、読み終わるまで時間を要した。小松真一氏の「虜人日記」に対し、山本七平氏が補足説明する。さらにかなり多くの注書。タイトルの通り、敗因21ヵ条が、日記に即して語られる。西南戦争と太平洋戦争の類似性の指摘、南京百人斬りなど、ここから発展するテーマ多し。読むべき本。されどまだまだ消化できず。力を蓄えて再び挑もう。2019/12/09
tama
21
図書館本 大変興味深く読んだ。中国侵略戦・太平洋戦争でなぜ負けたかについて。結局のところ勝算の見通しのないことをやり始めたからで、西郷隆盛が西南の役を起こして大敗したことと全く同じと解き、大戦のついこの前に国内で起きた事件なのに勝った官軍は負けた西郷の敗因を研究せず、同じ道を歩んだ、と。基本、科学技術屋の軍属だった方の日記「虜人日記」で話を進めているので、それも読もうと思ってます。「自由に語り合う」環境は基本的に日本人が持ちたがらないのかもしれない。2017/07/12
白義
19
小松真一の「虜人日記」というマイナーな名著を参照しながら、旧日本軍的な思考を徹底的に批判、さらにタイトルが「なぜ敗れるのか」と現在形になっていることからも明らかなように、その思考形式が構造をそっくりそのまま民主化した戦後まで引き継がれていることを指摘し弾劾する。観念とスローガンが現実認識を歪ませ、転倒させる精神主義、真の主体性がないゆえ自己中になり、鈍感に振る舞うがゆえ反日感情を買う。山本日本学の根幹が具体例で次々明らかにされるが、とりわけ飢餓と暴力性を語った部分が圧巻の出来2014/06/18
またおやぢ
18
我々は歴史から何を学び、何を考え、何を変えて来たのか…を考えさせられる。フィリピンに派遣された民間人、小松真一氏が著した『虜人日記』を軸に展開される、太平洋戦争の敗因分析。“現地”で“その時”に記された手記は、思想や合理性を追求することなく、また現状分析や論理の積み上げを行うことなく、精神論のみで組織を統制を目論んだ者達の末路を生々しく伝える。誰もが感じていた閉塞感に、声を上げぬ人々。いや、声をあげられない力が働いていとの指摘は、現在の社会にも流れる空気を思い起こさせる。反省無き世の中に警鐘を鳴らす一冊。2016/01/22