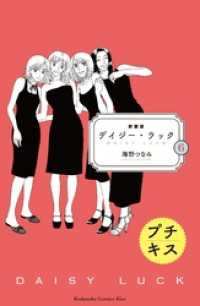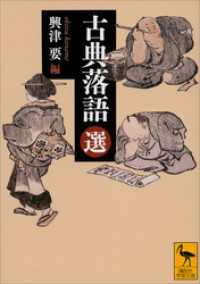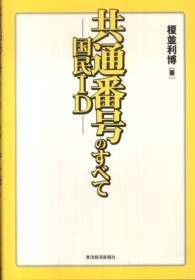- ホーム
- > 和書
- > 新書・選書
- > 教養
- > 角川oneテーマ21
内容説明
いまや全国の企業で昇進や昇格の評価からリストラの判断基準にまで、論文試験が採用されている。本書では論文の分析方法に基づいた有効な論文の書き方を、日本一の文章分析者が初めて実状に即して公開する。
目次
第1章 論文ひとつでクビになる?昇進昇格論文の実態(論文でサバイバル!;論文分析の視点;昇進昇格論文の実態)
第2章 昇進昇格の分かれ目はここだ(クビになる論文、昇進見送りの論文;論文試験八つのチェックポイント;実際に書いてみよう!)
著者等紹介
宮川俊彦[ミヤガワトシヒコ]
1954年、長野県に生まれる。国語作文教育研究所所長。小中学生を中心に100万人におよぶ作文を分析し指導、学校教育における文章力向上「作文教育」を提唱している。一方で、教育評論家としても活躍。テレビなどのコメンテーターとしても定評がある。また、大手上場企業など500社を超す「企業昇進昇格論文」や「入社試験の作文」などを開発、分析。日本で唯一の文章分析のスペシャリストとして、多岐にわたり活躍している
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kentaro
31
論文評価の基軸のひとつは現状認識。そして状況認識だ。今の自分がどういう場に置かれているかという世界の認識と周辺の認識がどの程度のものかということも含まれる。そこから進んで現状分析や状況分析の水準も問われる。これらは実際に論文に書かれているかどうかではない。書いても書かなくてもその水準は見えるものだ。実務論文では展開性や発展性が求められる。なぜなら基軸に柔軟さが必要だからだ。「私の見解は正しい。なぜなら」と理論をいくら作り上げても、実際の機動力がなくてはならないし、現実社会は常に変容と調整が求められる。2019/11/27
Artemis
16
昇格するにふさわしい、現状分析力を持っており、会社生活で渡っていくようなしたたかさ、現状打開する発想力、バランスが大事。にしても、文章の書き方で人格まで読み取れるなんてすごい読解力だと思う。そこまで読み方によっては人柄まで読み取れるってこと!たかが文章、されど文章。2018/06/15
Thinking_sketch_book
7
入社試験や昇格試験はこういう分析をしているのかと分かる。論文査読から行われる人格推測が警察の捜査と同じレベルで行われている。そう感じた。また本書を読むことで論文の書き方を基に自分の人生や、就職、昇進という事自体について、なんとも表現しがたい疑問が湧いてきた。数年後もう一度読んでみたい一冊だと思う。2012/05/26
YJ
6
辛口やね。仕事ぶりや人柄も論文で見透かされるらしい。為になりそう。実務論文において肝心なのは事例だ。事例を挙げることのみで視点も観点も思索も見解もわかる。昇進昇格論文の論理展開の本質:自己の見解→根拠や理由の提示→事例→事例を多角的に吟味検討する→結論。2017/06/03
かえるこ
3
論文から、その人の人間性や考え方などいろいろなことが読み取れるということに感心。「問題意識が基底にあってアイデアが生まれる/企業人は創造力や発想が常に求められる」。いざ書くときに困らないように、問題意識を持ちながら過ごしたい。それにしても、論文の本なのに文章が読みづらすぎて辛かった。助詞の使い方に違和感アリ(×相手を分からせる→○相手に分からせる、では?)、一般的に馴染みの薄い熟語を多用するなど。読解しやすい文章を書くのも大切かと。。2015/07/17