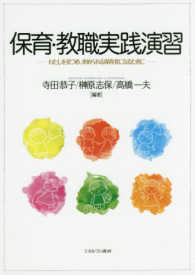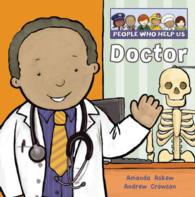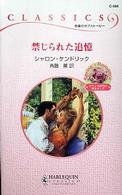内容説明
八番目の勅撰集『新古今和歌集』が編まれた時代は、和歌の黄金期である。新たな歌風が一気に生み出され、優れた宮廷歌人が輩出した。未曾有の規模の千五百番歌合、上皇自ら行う勅撰集の撰歌、と前例のない熱気をみせながら、宮廷の政治と文化は後鳥羽院の磁力のもと、再編成されていく。後鳥羽院と藤原定家という二つの強烈な個性がぶつかりあい、日本文化の金字塔が打ち立てられていく時代の熱い息吹に迫る。
目次
新古今時代の前夜
後鳥羽院歌壇始まる
女性歌人たちの活躍
『新古今和歌集』撰ばれる
後鳥羽院歌壇の隆盛
『新古今和歌集』の改訂と完成
帝王が支配する宮廷と文化
歌壇からはじかれた人々の開花
新古今歌壇の夕映
流謫の上皇
都に生きる定家
終焉と再生と
著者等紹介
田渕句美子[タブチクミコ]
1957年、東京都生まれ。お茶の水女子大学卒、同大学院博士課程単位取得。博士(人文科学)。大阪国際女子大学、国文学研究資料館を経て、早稲田大学教授。専門は中世の和歌、日記、歌人、女房に関する研究。文学と歴史の境を越え、中世の文学・文化を研究することに力を注ぐ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はちてん
28
通読しただけで感想を書く段階ではなくなのですが、院も定家もガンコ者でしかも美意識の固まり。新古今集が面白いのは当然かもしれません。載っている歌人も興味深い面々ですが、本書では時流に乗れなかった歌人にも言及されているので勉強になりました。2015/02/06
かな
5
新古今集が成立した背景、時代、関わった人々を、後鳥羽院と藤原定家という二人の人物を軸にして分かりやすく解説する本書は史実のドラマチックさも相まって大河ドラマのように大きくうねり展開してゆく。資料引用の際に、原文の後に親切な訳を載せてくれるので読みやすかった。日本史でいえば鎌倉時代、武家政権が成立したからといって王権が消えてしまうわけがなく、そういうなかで天皇を中心に文化を隆盛させることには、現代で想像しきれない意味があったのだろう。人々の華やぎが読んでいる私にまで移って熱に浮かされたような気持ちになった。2019/11/26
吉田裕子
4
細かな事実や近年の学説を丹念に追いながらも、読み物として面白いという奇跡のバランスの本。和歌に目覚めた後鳥羽院の熱、正治初度百首で一晩にして院の評価を得た定家の興奮、和歌所の活気。それらの空気が伝わる文章だ。ところで、遠島に流された上皇といえば、日本三大怨霊の崇徳院のイメージがあるけれど、後鳥羽院の隠岐での暮らしはそれと大きく違ったようだ。寂しいなかにあって矜持や文化を失わず、京とのやり取りもあり、遠島御歌合なる誌上歌合も企画されていた。新古今和歌集の再編を始めたのが、帰京が絶望視された頃なのだなぁ。2021/05/08
nininice
4
掘り下げて知りたい事柄や引用がたくさんあって面白く、勉強になりました。「物語二百番歌合」や、「有心無心連歌」など、とても興味深い!もっともっと新古今集時代を知りたいし、新古今集時代の後の時代にも興味が湧いてしまい、どこから始めれば良いのやら…!2017/01/12
Waka
3
田渕句美子氏の図書には何度かお世話になっており、一冊は引っ越しの餞別に頂いて愛読している。こちらも前から気になっていたものをようやく。 50頁、宮内卿を「藤原師光女」としているのは「源師光女」の誤りだろう。式子内親王の同母姉妹とされた休子内親王については、最新の研究では母が異なるとわかった、と4年後の著書に田渕氏自身が書いておられる。 丁寧な文章に、私も以前から信頼を寄せている。研究者としての冷静さを保ちながら、時折、あとがきなどに、並々ならぬ愛情の感じられる文章も。良書。勧めてくださった方に深謝。2019/06/07
-
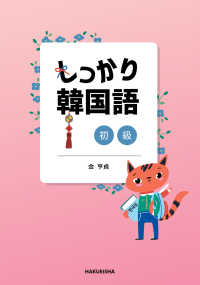
- 和書
- しっかり韓国語初級