内容説明
38億年前、生物が地球上に現れて以来、生物の細胞系列は生き続けてきた。性が誕生すると生物は劇的に変化し、限りない多様性やあらゆる能力と引き替えに、「死ぬ能力」をも獲得する。一回の生殖で一生分の精子を貯める女王バチ、口が退化し寿命が3日しかないアカシュウカクアリのオス、個体で性別を変化させるミミズ…。生物によって異なる性の決定システムから、ヒトの性にまつわる話まで、生物の性の不思議に迫る。
目次
第1章 なぜオスとメスがあるのか(何のためにオスとメスがあるのか;「性がある」デメリット ほか)
第2章 性の起源と死の起源(生命の起源;細菌の誕生 ほか)
第3章 性の進化(真核生物における性の起源;大小の誕生 ほか)
第4章 人間の性決定と性にまつわる話(女は実体、男は情報;人間の性を決定する遺伝子 ほか)
著者等紹介
池田清彦[イケダキヨヒコ]
1947年東京生まれ。現在、早稲田大学国際教養学部教授。構造主義科学論、構造主義生物学の見地から、多彩な評論活動を行う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
金城 雅大(きんじょう まさひろ)
22
種の多様性を性別という切り口で紹介している。生物界の広さに感嘆させられる。自爆テロのような戦略や、HUNTER×HUNTERの念能力を想起させる戦略を採る生物など、千差万別だ。そんな中、著者の主張は「生物界の性は割と適当」と一貫している。人間の性別に関するあれこれももちろん書かれている。内容に関しては、読んでみてのお楽しみということで。読んだ上での個人的意見としては、人間の場合は社会性という極めて大きな因子が付加されて複雑化するため、生物学論だけを持ってきて一概には言えないよなぁ、ってとこかな。2016/10/01
ゲオルギオ・ハーン
20
刺激的なタイトルだが、形式張らない書き方なので読みやすかった。そもそも生物が子孫を残す戦略についてや子孫を残さず不老不死ともいえるほどひたすら長生きする生物などを紹介。次にオスとメスを設定する利点は何か、オスとメスの違いはどういったものになるかとマクロからミクロへ視点を落としていく。生物学的に雌雄がある動物の傾向としては環境の変化に合わせて種を存続させる狙いがあり、誤解を恐れずに書くと子孫維持のために情報(DNA)を提供しているだけのオスは子孫が生まれたら死んでも問題はない。2025/02/06
Uzundk
13
こんにちは、生きているムダです。遺伝子の立場に立ってみると卵子(n倍体)が本丸であって身体(2n倍体)は箱である。卵子は本質的に不死だが卵にしかなれない。身体の細胞は複雑な構造を作る能力と共に死を得た。重要なのは遺伝子の多様性と修復で、不死性を保つ為には2つの遺伝子を掛け合わせて修復が必要になる。オスとは親(メス)の遺伝子の拡散のためのツールで、遺伝子も残せないくせにこいつらがのさばっていることは資源のムダであり、つきつめるとオスは生きているムダなのである。種をまいてとっとと死ねなのである。はい。2016/02/10
K K
7
面白かったー。メスは実態、オスは情報。そうなのかも。しかし、虫や他の動物はしたたかですね。人間なんて、甘っちょろい、甘っちょろい。婚活なんて可愛いもん。虫や動物の戦略が恐ろしい。肉団子をメスにプレゼントし、喜ぶメスを尻目にさっさと交尾をして、メスが肉団子を落としたら、他のメスにあげる。すごいのは、他のオスを殺して肉団子にする。人間のオスももっと頑張ってほしい(笑)草食化はことごとく摂理に反する。しかし、”ヒト”は、実は一夫多妻が本来の姿とはなんかわかる気がする。池田さん他も読もう!2016/09/13
のら@bowbow
7
参考文献を掲載するべき。どこがソースなんでしょうか。情報の洪水に飲まれている印象を受けた。これじゃ某まとめサイトと一緒だよ…2014/01/17
-

- 電子書籍
- 美と芸術のフェイズ - プラトンからコ…
-

- 電子書籍
- ある惑星の悲劇~ヒロシマ被爆者の記録~
-
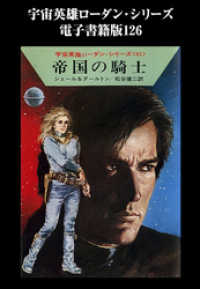
- 電子書籍
- 宇宙英雄ローダン・シリーズ 電子書籍版…
-
![モーニング 2016年28号 [2016年6月9日発売]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0333491.jpg)
- 電子書籍
- モーニング 2016年28号 [201…
-
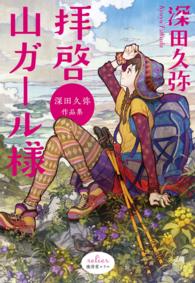
- 電子書籍
- 拝啓 山ガール様 深田久弥作品集 廣済…




