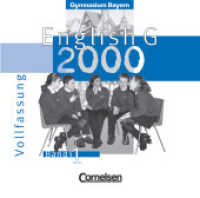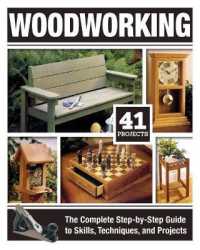内容説明
消滅した地名に秘められた歴史。新しくできた地名への人々の想い。地名改変が進むなか、社会の変化に伴い地名はどう変容してきたのか。「生き物」でありながら「無形文化財」として、過去と現在を結ぶ糸として人々の生活とともにある地名。そのでき方、つくられ方と魅力に迫る。
目次
第1章 地名はどのように誕生したか
第2章 地名の現場を訪ねて
第3章 地名の階層
第4章 市町村名の由来
第5章 駅名を分析する
第6章 地名崩壊の時代を迎えて
著者等紹介
今尾恵介[イマオケイスケ]
1959年横浜市生まれ。明治大学文学部独文専攻中退。管楽器専門誌「パイパーズ」編集部を経て91年より地名・地図・鉄道に関する執筆活動を開始。現在(財)日本地図センター客員研究員、日本国際地図学会評議員、関東学院大学非常勤講師。読売新聞夕刊にて「地図を歩く」を連載中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 消えた母は見知らぬ遺体になってここにい…