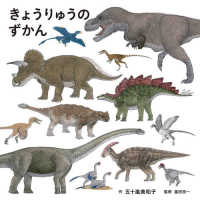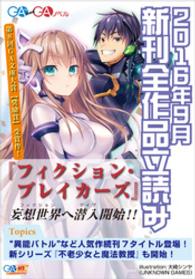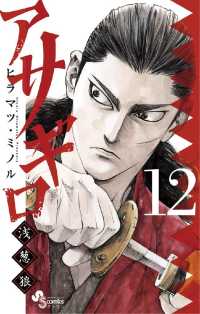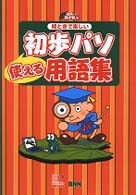内容説明
3世紀なかごろから7世紀初めまでの350年ほどの間に、列島各地に約5200基も造営された前方後円墳。その特質は「見せる王権」としての可視性、形状の画一性、大山古墳(仁徳陵)をピークとする墳丘規模の階層性にあり、大和政権を中心とした首長層ネットワークの「国家」と呼ぶべき利益共同体を表象するものだった。弥生から古墳時代の歴史を国家という枠組みで捉え直し、新たな歴史像を打ち立てる。
目次
第1章 首長はいかにして首長たりえたか
第2章 分業生産と交易の地域センターだった弥生都市
第3章 東アジア世界とカミ観念の形成
第4章 前方後円墳祭祀―国家をささえた共同幻想
第5章 “もの・人・情報の再分配システム”で成立した中央と地方
第6章 前方後円墳国家の誕生
第7章 前方後円墳国家を運営した大和政権
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
印度 洋一郎
1
350年間に渡って、日本の広い範囲で盛んに作られた前方後円墳。その変遷に、日本で初めての"国家"の誕生を読み解いている。この時代に先立つ弥生時代(恐らくは縄文時代から)の時点で、日本列島には情報や技術、物資の交換ネットワーク無くして成り立たない社会が出来上がっており、決して自給自足社会ではなかったと考察。その延長戦上に発展的に出現したのが、大和に発生した政権により成立した国家だという。古墳の変遷と他の資料との検証から、かなり具体的に全国統一→半島への軍事介入→体制の再編と強化→大君誕生という流れが浮かぶ。2011/07/16
遊動する旧石器人
0
前方後円墳国家という定義の説明はわかりやすかった。利益共同体であると。もの・人・情報の再分配システムで地方と中央が成立する。2013/11/01
ヘムレンしば
0
3世紀中ごろから7世紀はじめまで、日本全国で似たような形を持つ古墳が作られた時代がありました。考古学研究の発展により、縄文の昔から広範囲な地域交流ネットワーク、様々な分業体制があった事が判っているのですが、地方によってバラバラであったのが、この古墳を通じて画一的かつ大和を中心に階層性を持って纏っていくのが判ります。古墳、特にこの前方後円墳とは何か?そもそも国家とは何か?国家の形成について鋭く考察しています。2012/05/27