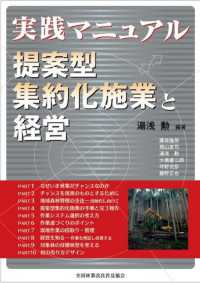内容説明
今日ますます深刻化する教育の荒廃ぶりは、管理教育の行きづまりを露呈している。本書は、管理教育を排し、個々の人間に生きがいのある人生を求めてやまないシュタイナーの「教育芸術」を、子どもの成長過程に則して、あますところなく解説する。
目次
1 零歳から7歳までの教育―幼児期の教育
2 7歳から14歳までの教育―小、中学生の教育(教育における感情の役割;子どもの教育を考えるときに忘れてならないもの;歴史の教育;教育の芸術的意味)
3 14歳から21歳までの教育―高校生の教育(教育における自我とアストラル体)
4 21歳から28歳までの教育―第4・7年期の教育(教育における意識魂と悟性魂)
5 母親の自己教育―生涯の教育(自己教育を考える)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
デビっちん
27
再読。アニメ、エヴァンゲリオンのパイロットが14歳までなのは、シュタイナーの7歳周期での成長が関係しているのではないか説が生まれました。そんな7歳から14歳の教育を行うには、子どもの気質を知り、自分の気質を知ることが必要です。感情が成長する第ニ7年周期、その教育を楽しみに、意志力の教育に力を入れていこうと思います。2018/06/24
デビっちん
12
教育は芸術である。この一言に痺れました。シュタイナー氏の教育の全体像は、人間を4つの気質と7歳を区切りとした4段階に分けて行うという構造の教育形態です。4つの段階で特に感銘を受けたのが、7歳から14歳までの期間で、特に感情の教育を行う段階です。ここで芸術教育が説明されていました。自分に対して芸術的な態度をとることは、自分のイメージと自分との関係を深くすることに役立ちます。それは、物質的な世界と内面的な世界とを繋ぐ架け橋になります。五感を中心にしたどんな教育ができるだろう?2016/03/22
Gotoran
5
日本の悲惨な教育状況に警鐘を鳴らすために、シュタイナー思想の観点から、0歳~7歳、7歳~14歳、14歳~21歳、21歳~28歳、28歳以降と、成長の過程を辿って、考察されている。シュタイナー教育とは、人間関係の教育であり社会教育であると記されている。感情・心に根ざした人に優しい考え方。本当に生甲斐のある人生をこの世で送るためには、芸術的な態度を人生のあらゆる側面において貫くことが大切に共感。約20年前の著作ではあるが今でも示唆に富んでいる。ホリスティックな在り方を大切にしたいものだ。再読本の1つ。2011/04/01
ひつまぶし
3
神秘主義の部分が結構ぶっ飛んでいたので、すでに社会的に受容されているシュタイナー教育から入ってみることにした。著者なりの解説なので出処が不明だが、感覚魂・悟性魂・意識魂など、ただシュタイナーを読んでいるだけでは分かりにくかっただろう頻出用語の理解も進められた。問題を心地よく効率よくクリアできる道ではなく、困難と知ってなおそれに挑むことが自由なのだというシュタイナーのスタンスには感銘を受けた。教育という形だが、自己教育という形でずっと続いていくし、社会生活の中で他者とどう付き合うかにも通じるものだと思った。2025/04/16
SAJOU
1
《図書館の本》教育関係者が読む物かと思ったが、あらゆる人を対象にした内容といっていいのではと感じた。親である自分も自己教育が必要。「人を信頼し続ける」ことの意味。「自分にとって異質なものにどこまで自分が関われるか」「努力し迷って生きていることに生きがいを感じられる魂であれ」など気づかされること多し。2012/06/14
-
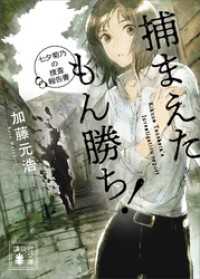
- 電子書籍
- 捕まえたもん勝ち! 七夕菊乃の捜査報告…
-

- 和書
- 中小企業の情報活用戦略