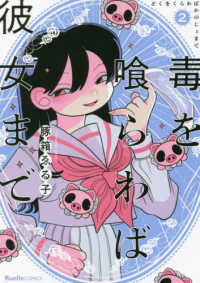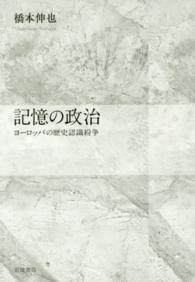出版社内容情報
1931?45年の戦間期、日本のまんが界では二者が奇妙な邂逅をとげる。ディズニーと、映画界の巨匠エイゼンシュテインの手法だ。両者の美学が溶け合い、手塚治虫、ジブリへとつながる。画期的な近代まんが史。
内容説明
世界に誇る日本のまんがやアニメーションは、手塚治虫の手法で語られることが多い。だが、前史を丹念に追っていくと、その起源は一九三一~四五年の十五年戦争期にあった。当時、まんがやアニメーションがプロパガンダの一端を担っていく中で、ディズニーのアニメと、エイゼンシュテインをはじめとするロシアアヴァンギャルドが奇妙な邂逅をみたのだ。両者の統合によって生まれ、洗練された美学が手塚らに影響を与え、現在のジブリへとつながっていく。日本まんが史の再構築を促す画期的論考。
目次
序 ディズニーとアヴァンギャルドの野合―外国の人々に向けた日本まんがアニメ史
第1章 「ミッキーの書式」とまんが記号説(まんが記号説の起源と「略画式」的思考の近代的書き換え;『正チャンの冒険』とキャラクターの固有性の発生 ほか)
第2章 「科学」という統制と映像的手法の発生(「科学」と児童読物統制;小熊秀雄という問題 ほか)
第3章 「文化映画」としての『桃太郎海の神兵』―今村太平の批評を手懸りとして(「文化映画」とは何か;「文化映画」に於けるストーリーの排除 ほか)
補論 「戦争画」という問題―戦時下のアニメーション、まんがとの対比で(残虐さという問題;「ごっこ」と残虐さ)
著者等紹介
大塚英志[オオツカエイジ]
1958年生まれ。筑波大学人文学類で民俗学を専攻。その後、フリーの編集者としてまんが雑誌などに携わり、まんがの原作、および評論など多岐にわたり活躍。現在、国際日本文化研究センター客員教授。著書に、『「捨て子」たちの民俗学―小泉八雲と柳田國男』(角川選書、第五回角川財団学芸賞)、『戦後まんがの表現空間』(法藏館、第十六回サントリー学芸賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
yyhhyy
seichan
わとそん