出版社内容情報
『この俳句がスゴい!』の著者による、絶品俳句鑑賞の第2弾。杉田久女、橋本多佳子、寺山修司など個性派俳人16名の作品を鋭い見識と愛情を込めて深く読み解き、作家像に迫ります。秀句が著者の鑑賞で名句になる!
内容説明
杉田久女、橋本多佳子、寺山修司など16名の個性派俳人の名句を読み解く。名句はなにゆえ名句なのか。俳人の内側にまで迫る確かな筆致で広がる名句の世界。「これが名句だ!」と思わず膝を叩くこと間違いなし。はっと驚き、すとんと納得。俳句の面白さを凝縮した大人の名句鑑賞。
目次
杉田久女
川端茅舎
橋本多佳子
阿波野青畝
横山白虹
中村草田男
東京三(秋元不死男)
富沢赤黄男
星野立子
鈴木真砂女
松本たかし
安住敦
中村苑子
木下夕爾
佐藤鬼房
寺山修司
著者等紹介
小林恭二[コバヤシキョウジ]
昭和32年、兵庫生まれ。昭和56年、東京大学文学部卒業。在学中は、東大俳句会に在籍。昭和59年、小説『電話男』が第3回海燕新人文学賞を受賞。昭和60年、『小説伝』が第94回芥川賞候補となる。平成10年、『カブキの日』で第11回三島由紀夫賞を受賞。現在、専修大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
harass
58
『この俳句がスゴい! 』の続編。16人の俳人たちを語る雑誌記事をまとめたもので、今回取り上げている寺山修司をどう評価しているのかを読みたくて借りる。著者は寺山の俳句の盗作問題はクロとし、本歌取りだとしても本歌取りのルール違反であると。だが作品の魅力に抗えないという。著者は苦しげにTSエリオットの引用をする。「未熟な詩人は贋物を作り、熟練した詩人は盗作する。だめな詩人は原作を損ない、良い詩人は原作を更に良いものにするが、少なくともまったく違うものにする。」2018/05/10
メタボン
25
☆☆☆ 俳句の読み方には戸惑うが、小林恭二の「読み」はわかりやすく、同氏が選者となった俳句本は手に取ってしまう。花衣ぬぐやまつはる紐いろいろ(杉田久女)蛍籠昏ければ揺り炎えたたす(橋本多佳子)降る雪や明治は遠くなりにけり(中村草田男)~この句は切字を二つ使ってルール違反なれども名句はやはり名句。同じ草田男の、万緑の中や吾子の歯生え初むる~無季語の句だがこの句により万緑は季語となった。真直ぐ往けと白痴が指しぬ秋の道(草田男)蝶堕ちて大音響の結氷期(富沢赤黄男)冬の蠅病めばかろがろ抱かれもし(鈴木真砂女)。2019/05/19
しーふぉ
14
取り上げている俳人で1番有名なのは寺山修司か⁈杉田久女や川端茅舎など俳句に詳しい人には常識なのかもしれないが、素人には初めて聞く俳人の作品を楽しく鑑賞出来ました。丁寧に俳人の説明や俳句の説明があったのが良かったです。2019/10/13
オールド・ボリシェビク
3
再読か、三読か。小林恭二という人の俳句の読みを、私はかなり、信頼しているのだ。本書で取り上げられいる俳人は杉田久女、川端茅舎、橋本多佳子から寺山修司まで16人。特に中村草田男の論考は読み応えあり。人間性に対しては微塵の疑いもないが、形式に対する感覚には相容れないものがあるとしたうえで、「しかしわたしは彼を認めます。彼のような人がいたからこそ、日本の俳句は、ひいては日本の文芸はより豊饒になったのですから」とする。また飯田龍太が寺山修司を「盗作の度が過ぎるから」と評したというエピソードもなかなか凄みがある。2022/06/05
azimuth
2
俳人16名の略歴と句の鑑賞。この句にはAとBという読みがありうるが、こういう理由からAであろうと筆者は思う、Bはこういう理由から採用しない、式の論理的な説明が初心者に有難い。この類の本は筆者の好みに無意識のうちに影響されてしまいがちなので警戒してかかるようにしているのだが、この筆者は無頓着なまでに自分がどちらの側にいるかを明かして語っているので、公平で良い。もともと好きな寺山修司をのぞくと、阿波野青畝とか星野立子が気になった。あと、草田男。かの有名な、万緑の中や、が無季俳句だったなんて思いもよらなかった。2014/10/13
-
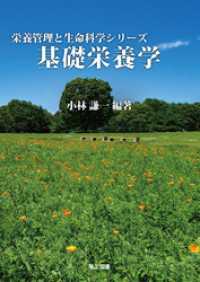
- 電子書籍
- (栄養管理と生命科学シリーズ) 基礎栄…
-
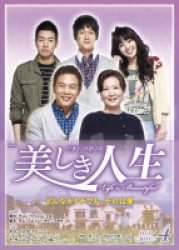
- DVD
- 美しき人生 DVD-BOXⅣ






