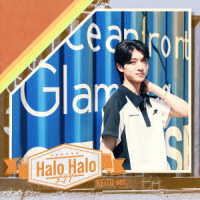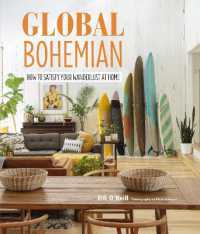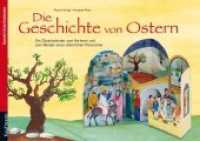内容説明
『信長公記』は織田信長の旧臣・太田和泉守牛一が、慶長十五年(一六一〇)頃に完成させた、信長の一代記である。首巻一巻と本記十五巻の全十六巻からなり、信長の生誕から本能寺における謀殺までの生涯が、全編リアルな筆致で記述されている。信長の姿を真近で実見していた側近による記録なので、その信頼性は高く、歴史書としても一級史料と評価されている。本書では原文を時系列に並べ替え、主語を明確に補い、人名を通称から実名に改めるなど、現代語に直訳しただけではわかりにくい文章を、平易に読めるように工夫した。
目次
尾張の国、上の郡と下の郡
小豆坂の合戦
吉法師、元服
織田信秀、美濃へ侵攻
平景清所持の名刀あざ丸
織田信秀、大柿城を救援
青年信長の日常
犬山衆、謀反
織田信秀、病死
三の山・赤塚の合戦〔ほか〕
著者等紹介
太田牛一[オオタギュウイチ]
大永7年(1527)~慶長18年(1613)。織田信長の側近として、活躍する。本能寺の変後、豊臣秀吉に召し出された。文才にも恵まれ、同時代の名将たちの伝記を書き残した
中川太古[ナカガワタイコ]
1934年、東京都八王子市に生まれる。國學院大學文学部文学科を卒業。出版社に勤務し、歴史・美術・芸能・民俗関係の出版企画・編集を担当。1990年に退社し、現在はフリーの編集者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
優希
51
信長の「一代記」を知ることができる1冊です。信長の生涯を間近で見てきた側近の記録なので、様々な発見がありました。壮絶な出来事も淡々と描いている印象ですが、いた人、辞世の句、状況なども知ることができると思います。記録視力にはただ脱帽としか言えません。信長がどのような人物か興味深く読みました。2025/05/08
saga
42
信長に興味を抱いていたところに現代語訳の本書を入手。戦国時代とはよく言ったものと痛感。その中で信長が生き抜いていく様子がよく判る。しかし攻め下した敵将やその一族に対する生殺与奪の仕方に統一性が見られず、特に成敗という名の殺戮を記したくだりは痛ましい。終盤に甲斐の国から帰陣する道中は東海道の宿場町として残っている地名が多く、そこだけ平和な道中記を読むようだった。本記は明智光秀謀反から安土城留守居衆の様子、家康が堺から退去していくところで終わっている。他の文献でその後の様子が知りたくなった。2016/03/24
hiro-yo
28
普段歴史に触れる機会は無いのだが、歴史書を読む自分に酔ってみたいと思い拝読。ただ現代語訳だし、単発のエピソードごとの短章構成になっているので入門レベル。信長のWIKIと併せて読むと概要と本誌記述がセットで読めるて分かりやすい。戦国時代に生きた信長の野心に魅せられた。「信長は、その場限りの喧嘩をしていると思ったのだが、全くそうではなかった。明智勢は鬨の声を上げ、御殿へ鉄砲を撃ち込んできた。信長が「さては謀反だな、誰のしわざか」と問いただすと、「明智の軍勢と見受けます」と答えた。信長は「やむをえぬ」と一言。」2021/11/12
春風
21
織田信長に仕えた武士である、太田牛一による織田信長の一代記の現代語訳。信長研究の最重要文献である。『信長公記』は牛一自筆のものでも数点伝わっているが、本現代語訳は新人物往来社『改訂 信長公記』を底本にしているとの事なので、武勲神社所蔵の写本に拠っている事となるであろうか。入京以前を扱った「首巻」も収録され、巻一〜巻十五まで収録。注釈も多いが他文献との異同などは記されず、その殆どが地名の現住所を表しているに過ぎないので、史料としてよりも物語に価値を置いた一冊といえる。2020/09/22
OCEAN8380
21
信長の棺を読んで大田牛一に興味が持てたので読んでました。現代語に訳されていたので読みやすかったです。信長が戦国時代をどのように生き抜いていたかよく分かりました。信長は非道な面があるが部下が手柄を上げれば報酬を賜る人柄としては良いと思いました。2016/04/05