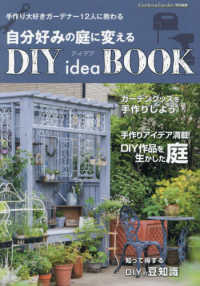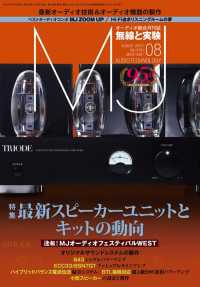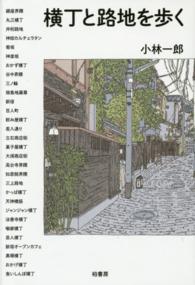出版社内容情報
80年代の終わり、子供たちはなぜビックリマンシールや都市伝説に熱狂したのか?「大きな物語」の終焉と、ネット上で誰もが作者になる現代を予見した幻の消費社会論。新たに「都市伝説論」を加え、待望の文庫化なる!!
内容説明
1980年代の終わりに、子供たちは「ビックリマンチョコレート」のシールを集め、「人面犬」などの都市伝説に熱狂した。それは、消費者が商品の作り手が作り出した物語に満足できず、消費者自らの手で物語を作り上げる時代の予兆であった。1989年に於ける「大きな物語」の終焉を出発点に、読者が自分たちが消費する物語を自分たちで捏造する時代の到来を予見した幻の消費社会論。新たに「都市伝説論」を加えて、待望の文庫化!巻末に’80年代サブカルチャー年表を付ける
目次
1 物語消費論ノート
2 複製される物語
3 消費される物語
4 再生する物語
短い終章 手塚治虫と物語の終わり
補 都市伝説論
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
harass
74
1989年の本に補講をつけた文庫(2001)。著者の物語消費論を参考にした東浩紀は、データベース消費論を生み出すことになる。ビックリマンチョコなどを例に、設定やドラマの断片を見せ、ユーザーにその背後の物語を想像させるスタイルの作品を解説。80年代当時の文化の事象を考察していく。正直、古く感じるのだが、今から見ると常識に思える部分がある。またあとがきに著者が絶版予定のこの本を再販した理由がある。80年代はまだ続いているという確信があるという。準古典、資料として。2018/10/07
へくとぱすかる
46
原著は1989年。復刻版のこの文庫が2001年。今はさらにそれから15年も経っている。というのが信じられないほどである。何だかんだ言って、この社会は現在も80年代を引きずっているように見える。「噂」についても、インターネットのおかげで、より浸透していると思えるし。それにしても「物語」というキーワードを媒介にして結びつく、宗教とビックリマンとの類似に対する指摘は衝撃。2016/11/21
ころこ
36
いわゆるサーガ論で、著者は『スターウォーズ』をよく例に出す。ゲームマスターが〈物語世界〉の枠組みを作って、個々の作品は別の作家が作成する。ゲームマスターからみれば、別の作家は物語の消費者だ。二次創作やデータベース消費、スピンアウトものなど、現在では当然のように行われていて、当時は無限にあるようにみえた物語論の参照枠をつくった。本書はビックリマンによる説明を前面に出している。シールがおまけに付いているチョコレートの製品を、子供たちがおまけのシールの方に熱狂してチョコレートを食べないで捨ててしまう否定的に報道2023/03/27
hanchyan@そうそう そういう感じ
28
というわけで私淑する大塚さん。何度めかの再読です。ここ何日かのつぶやきでの抜粋はコレがネタ本でした。開巻の「1 世界と趣向ー物語の複製と消費」から試みに固有名詞だけを抜き出してみると、ボードリヤール・ビックリマンチョコ・グリコ・仮面ライダースナック・石ノ森章太郎・仮面ライダー・出口王仁三郎・マハーバーラタ……とまあ、ここまで2ページ。んで、『キャプ翼同人誌』について歌舞伎における『趣向』を使っての解説へと続きます。なんかそんな感じの本。ん。あー。何度読んでもやっぱものすごく面白い(※当社比です)。2025/10/24
ヤギ郎
18
東浩紀以前のサブカルチャー論。著者のあとがきから,本書で紹介された議論は「古い」ものであるけれども,その再構築により,現代にも通用する議論となる。著者よりはるか後に生まれた世代として,80年代・90年代の言説に触れることのできるよい資料である。著者の目を通じてみる「天皇論」は興味深い。社会が成熟し,新たなコンテンツが誕生した現代社会において,私たちの消費行動を見つめ直す一冊になるといえよう。2019/04/22